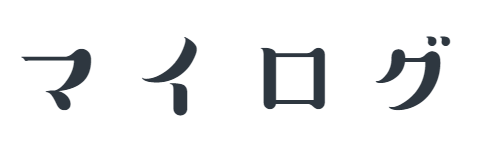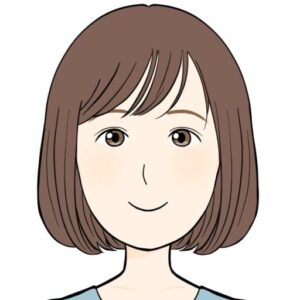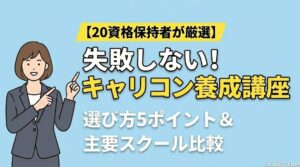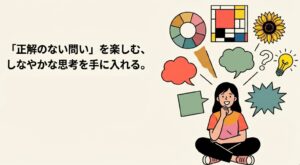ブログ案内犬しろちゃん
ブログ案内犬しろちゃん「何か専門的な資格が欲しいな…」
「健康や医薬品に興味がある」
「安定して長く働ける仕事を見つけたい」



そんなあなたに、今注目されている登録販売者という資格をご紹介します。
登録販売者は、ドラッグストアや薬局などで一般用医薬品(かぜ薬や鎮痛剤など)の販売ができる専門家です。受験資格に学歴や実務経験が不要なため、未経験からでも挑戦できる国家資格として人気が高まっています。
近年、セルフメディケーション(自分自身で健康を管理すること)の重要性が高まる中、医薬品の専門知識を持つ登録販売者の社会的ニーズはますます増加しています。



この記事では、登録販売者に興味を持ち始めたあなたに向けて、以下の内容を分かりやすく解説していきます。
- 登録販売者ってどんな仕事?具体的な業務内容は?
- 試験の難易度や合格率、費用は?
- 資格を取るメリットと将来性
- 効率的な勉強法とおすすめ教材
- 合格後のキャリアパスと給与事情
最後まで読めば、「自分も登録販売者を目指せそう!」と具体的なイメージが湧いてくるはずです。



ぜひチェックしてね!
登録販売者ってどんなお仕事?仕事内容を詳しく解説


登録販売者の主な仕事は、一般用医薬品(OTC医薬品)の専門家として、お客様の健康をサポートすること。



「かかりつけの薬の専門家」として、地域の人々の健康を身近で支える重要な役割を担います。
一般用医薬品とは?登録販売者が扱える医薬品
一般用医薬品は、医師の処方箋なしで購入できる医薬品のこと。リスクの程度に応じて3つに分類されています。
| 分類 | 特徴 | 主な医薬品例 | 販売できる人 |
|---|---|---|---|
| 第1類医薬品 | リスクが高い | ロキソニンS、ガスター10など | 薬剤師のみ |
| 第2類医薬品 | リスクが中程度 | かぜ薬、解熱鎮痛薬、胃腸薬など | 薬剤師・登録販売者 |
| 第3類医薬品 | リスクが低い | ビタミン剤、整腸薬など | 薬剤師・登録販売者 |
登録販売者は第2類医薬品と第3類医薬品を販売できます。



全医薬品の約9割以上に該当するため、ドラッグストアで扱うほとんどの医薬品を取り扱えることになります。
主な業務内容
1. 医薬品の販売・カウンセリング業務
お客様一人ひとりの症状や体質に合わせた提案を行う、専門性の高い業務です。
- 症状のヒアリング:「どのような症状ですか?」「いつからですか?」など詳しく聞き取り
- 適切な医薬品の提案:症状に合った医薬品を選び、分かりやすく説明
- 服用方法の説明:用法・用量、服用タイミング、注意事項の説明
- 副作用や相互作用の説明:他の薬との飲み合わせ、副作用のリスクについて情報提供
- 受診勧奨:症状が重い場合や医薬品では対応できない場合、医療機関の受診を促す
単に薬を売るのではなく、お客様の健康状態を考慮し、時には「これは病院に行った方がいいですよ」とアドバイスすることも大切な仕事です。
2. 健康相談・情報提供
- 生活習慣のアドバイス:食事、運動、睡眠など健康的な生活習慣の提案
- 予防・未病対策の提案:サプリメントや健康食品の紹介
- 季節の健康情報提供:花粉症対策、熱中症予防、インフルエンザ対策など
- 妊娠中・授乳中の相談対応:服用できる医薬品の案内
3. 店舗運営・医薬品管理業務
- 医薬品の発注・在庫管理:欠品がないよう適切な在庫を維持
- 品質管理:使用期限のチェック、適切な保管状態の維持
- 売り場のレイアウト作成:お客様が選びやすい売り場づくり
- POPやポスターの作成:商品の特徴を分かりやすく伝える販促物の作成
- 新人教育・スタッフ指導:経験を積むと後輩の指導も担当
4. 店舗管理者としての業務(実務経験2年以上)
登録販売者として2年以上の実務経験を積むと、「店舗管理者」として薬剤師がいない店舗でも医薬品販売を管理できるようになります。
- 店舗全体の医薬品販売の責任者
- スタッフの管理・シフト作成
- 店舗の売上管理
- 店長としてのキャリアパス
お客様から「ありがとう、楽になったよ」「あなたに相談してよかった」と直接感謝されることも多く、人の役に立っている実感を得られる、非常にやりがいのあるお仕事です。
働ける場所は?



登録販売者の活躍の場は年々広がっています。
- ドラッグストア:最も求人が多く、キャリアアップしやすい
- 調剤薬局・薬店:地域密着型で信頼関係を築きやすい
- コンビニエンスストア:医薬品取り扱い店舗が増加中
- スーパーマーケット:食品と医薬品の両方を扱う大型店
- ホームセンター:生活用品とともに医薬品コーナーを設置
- 家電量販店:健康機器とともに医薬品も販売
- 通販・EC企業:オンライン薬販売の拡大で需要増加
2009年の法改正により、一般用医薬品をネット販売できるようになったことで、ECサイトでの登録販売者の需要も高まっています。
登録販売者試験とは?難易度・合格率・費用を徹底解説


登録販売者は、都道府県が実施する試験に合格することで取得できる国家資格です。2015年の法改正により受験資格が撤廃され、誰でも受験できるようになりました。
試験の基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 資格の種類 | 国家資格 |
| 受験資格 | 学歴・実務経験・年齢など一切不問(誰でも受験可能) |
| 難易度 | ★★☆(普通) |
| 合格率 | 全国平均 約40〜50%(都道府県により差あり) |
| 受験費用 | 13,000円〜18,600円程度(都道府県により異なる) |
| 試験日 | 年1回(都道府県ブロックごとに8月〜12月の間で実施) |
| 試験時間 | 午前・午後合わせて約240分(4時間) |
| 試験形式 | マークシート式(五肢択一) |
| 問題数 | 120問 |
試験科目と出題数
| 科目 | 出題数 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1章:医薬品に共通する特性と基本的な知識 | 20問 | 医薬品の副作用、相互作用、服用方法など |
| 第2章:人体の働きと医薬品 | 20問 | 体の構造、各臓器の働き、症状が起こるメカニズム |
| 第3章:主な医薬品とその作用 | 40問 | 最重要科目。各医薬品の成分、効果、副作用 |
| 第4章:薬事関係法規・制度 | 20問 | 医薬品医療機器等法などの法律知識 |
| 第5章:医薬品の適正使用・安全対策 | 20問 | 添付文書の読み方、副作用報告制度など |
合格基準
合格には以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
- 総合得点が70%以上(84点以上/120点)
- 各科目で35〜40%以上の得点(足切りライン。都道府県により異なる)
つまり、総合点が高くても、1科目でも極端に点数が低いと不合格になってしまいます。バランスよく学習することが重要です。
合格率の推移と都道府県別の傾向



全国平均の合格率は約40〜50%ですが、都道府県によって大きく差があります。



知らなかった……!そういうこともあるよね……!
合格率が高い傾向の都道府県
- 北海道・東北ブロック:50〜60%前後
- 北陸・東海ブロック:50%前後
合格率が低い傾向の都道府県
- 関西ブロック:30〜40%前後
- 首都圏ブロック:40%前後
※年度によって変動があります
ポイント:合格率が高い都道府県で受験するのも一つの戦略です。住民票がなくても受験できるため、複数の都道府県で受験する方もいます。
試験日程(都道府県ブロック別)
全国を複数のブロックに分け、それぞれ異なる日程で実施されます。
- 関東・甲信越ブロック:8月下旬〜9月上旬
- 北海道・東北ブロック:9月中旬
- 東海・北陸ブロック:9月下旬
- 関西広域連合:10月上旬
- 九州・沖縄ブロック:10月中旬〜11月
ポイント:複数のブロックで受験することで、合格のチャンスが増えます。
公式情報サイト
- 厚生労働省 登録販売者試験について:https://www.mhlw.go.jp/
- 各都道府県の薬務課:試験日程・申込方法は各都道府県のウェブサイトで確認
登録販売者の資格を取るメリット・将来性


資格取得の7つの大きなメリット
1. 就職・転職で圧倒的に有利
ドラッグストア業界は慢性的な人手不足。登録販売者の求人は全国各地で豊富にあり、**就職率はほぼ100%**と言われています。特に地方や郊外では、資格保有者は引く手あまたです。
2. 資格手当で収入アップ
多くの企業で資格手当が支給されます。
- 資格手当の相場:月3,000円〜20,000円
- 年収換算:36,000円〜240,000円の収入増
長期的に見れば大きな収入差になります。
3. 誰でも受験できる国家資格
学歴や実務経験が不要で、年齢制限もありません。高校生から60代以上の方まで、幅広い年齢層が合格しています。国家資格でありながらこれほど門戸が広い資格は珍しく、チャレンジしやすいのが魅力です。
4. 全国どこでも働ける
医薬品を扱う店舗は全国にあるため、引っ越しや転勤があっても仕事を見つけやすいです。地方移住を考えている方にも適した資格です。
5. キャリアアップのチャンスが豊富
- 店舗管理者・店長:実務経験2年以上で店舗管理者になれる
- エリアマネージャー:複数店舗を統括する管理職
- 本部スタッフ:商品開発、バイヤー、教育担当など
- 講師・インストラクター:登録販売者の育成担当
6. 働き方が選べる
- 正社員:安定収入とキャリアパス
- パート・アルバイト:週2〜3日、短時間勤務など柔軟な働き方
- 派遣社員:高時給で様々な職場を経験
- ダブルワーク:土日のみ、夜間のみなど副業として
ライフスタイルに合わせて働き方を選べるのは大きな魅力です。
7. 自分や家族の健康管理に役立つ
医薬品の知識は、自分自身や家族の健康管理に直接活かせます。「この症状にはこの薬」「この成分は子どもには使えない」など、実生活で役立つ知識が身につきます。
将来性と社会的ニーズ
セルフメディケーションの推進
政府は、軽い病気は自分で医薬品を使って治す「セルフメディケーション」を推進しています。医療費削減の観点からも、一般用医薬品の活用が推奨されており、その専門家である登録販売者の需要は今後さらに高まると予想されます。
高齢化社会での役割
高齢者人口の増加に伴い、健康相談や医薬品アドバイスのニーズが拡大。「かかりつけの薬の専門家」として地域で頼られる存在になれます。
ネット販売の拡大
オンラインでの医薬品販売が拡大する中、EC企業でも登録販売者の採用が増えています。在宅勤務で医薬品のオンライン相談に対応する仕事も登場しています。
新たな活躍の場
- 企業の健康管理部門:社員の健康相談担当
- 介護施設:入居者の健康サポート
- スポーツ施設:アスリートの薬のアドバイス
登録販売者の活躍の場は、今後さらに多様化していくでしょう。
おすすめの勉強方法を徹底比較!効率的な学習法とは
試験合格のための勉強方法は、主に3つあります。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
1. 独学
費用:約5,000円〜10,000円(テキスト・問題集代のみ) 学習期間の目安:3〜6ヶ月
メリット
- 費用を最も安く抑えられる
- 自分のペースで学習できる
- 好きな時間に好きな場所で勉強できる
デメリット
- 学習計画をすべて自分で立てる必要がある
- 専門的な内容で理解が難しく、挫折しやすい
- 疑問点を質問できる相手がいない
- モチベーション維持が難しい
こんな人におすすめ
- とにかく費用を抑えたい方
- 自己管理能力があり、コツコツ勉強できる方
- 医療や薬学の基礎知識がある方
おすすめテキスト
【基本テキスト】
- 『7日間でうかる! 登録販売者 テキスト&問題集』(KADOKAWA)
- 初心者向けで分かりやすい。イラスト豊富
- 『ユーキャンの登録販売者 速習テキスト&重要過去問題集』(U-CAN)
- 効率的に学べる構成。重要ポイントが明確
- 『登録販売者 合格教本』(中央法規出版)
- 詳しい解説で理解が深まる。じっくり学びたい方向け
【問題集】
- 『登録販売者試験 過去問題集』(各都道府県版)
- 『登録販売者 試験問題作成の手引き準拠 模擬試験問題集』
重要:最新年度の「試験問題作成の手引き」に準拠した教材を選びましょう。医薬品の情報は更新されるため、古いテキストでは対応できない場合があります。
2. 通信講座
費用:約30,000円〜50,000円 学習期間の目安:3〜6ヶ月
メリット
- 合格へのノウハウが詰まった効率的なカリキュラム
- 質問サポートが受けられる(メール・郵送など)
- 添削指導で自分の理解度を確認できる
- 最新の試験傾向に対応した教材
- スマホやタブレットで学習できる講座もあり
- 就職サポートが付いている講座もある
デメリット
- 独学よりは費用がかかる
- 通学と比べると直接質問できない
こんな人におすすめ
- 効率的に確実に合格したい方
- 自宅で学びたいけれど、独学は不安という方
- 仕事や家事・育児をしながら資格取得を目指す方
- サポート体制が整った環境で学びたい方
主要な通信講座
【ユーキャン 登録販売者講座】
- 費用:49,000円(税込)
- 標準学習期間:6ヶ月
- 特徴:初心者向けのわかりやすい教材、充実した質問サポート、添削8回
- スマホ学習対応
【たのまな(ヒューマンアカデミー)登録販売者合格講座】
- 費用:37,000円〜
- 標準学習期間:6ヶ月
- 特徴:eラーニング対応、就職サポートあり、質問無制限
【三幸医療カレッジ 登録販売者受験対策講座】
- 費用:35,000円〜
- 標準学習期間:3ヶ月〜
- 特徴:医療教育専門校の実績、合格率が高い、実務に役立つ内容
【キャリカレ 登録販売者合格指導講座】
- 費用:38,500円(税込)
- 標準学習期間:3ヶ月
- 特徴:不合格なら全額返金制度あり(条件あり)、スマホ学習対応
3. 通学講座(スクール)
費用:約60,000円〜150,000円 学習期間の目安:1〜3ヶ月(短期集中コースあり)
メリット
- 講師から直接指導を受けられる
- その場で疑問点を質問・解決できる
- 一緒に学ぶ仲間がいるため、モチベーションを維持しやすい
- 実習や模擬演習で実践的なスキルが身につく
- 短期集中で効率的に学べる
- 就職サポートが手厚い
デメリット
- 費用が最も高い
- 決まった時間に決まった場所へ通う必要がある
- 地方では通学できるスクールが限られる
こんな人におすすめ
- 短期間で確実に合格したい方
- 一人では勉強が続かない、仲間と一緒に学びたい方
- 講師に直接質問しながらしっかり理解したい方
- 通学できる範囲にスクールがある方
主要なスクール
- 三幸医療カレッジ(全国展開)
- 日本医療事務協会
- ニチイ学館
- 資格の大原
学習方法選びのフローチャート
Q1. 費用を最優先で抑えたい? → YES:独学がおすすめ
Q2. 自宅で学びたい? → YES:通信講座がおすすめ → NO:通学講座を検討
Q3. 一人で勉強を続ける自信がある? → YES:独学or通信講座 → NO:通学講座がおすすめ
Q4. できるだけ早く資格を取りたい? → YES:通学講座(短期集中コース) → NO:通信講座で自分のペースで
合格するための効率的な学習戦略
学習スケジュールの立て方
【6ヶ月プラン(標準的)】
1〜2ヶ月目:基礎知識のインプット
- 第1章〜第5章まで一通りテキストを読む
- 人体の構造、各章の全体像を把握
- わからない部分があっても気にせず先に進む
3〜4ヶ月目:重点学習と理解を深める
- 第3章(主な医薬品とその作用)を重点的に学習
- 最も出題数が多く、重要な章
- 成分名、効能効果、副作用を覚える
- 第2章(人体の働き)を丁寧に復習
- 医薬品がなぜ効くのか、体の仕組みから理解
5ヶ月目:過去問演習・弱点克服
- 過去問題を繰り返し解く(3〜5年分)
- 間違えた問題を重点的に復習
- 苦手な章・分野を集中的に学習
6ヶ月目:総仕上げ・模擬試験
- 模擬試験を時間を計って解く(本番の練習)
- 最終確認・暗記事項の総復習
- 試験1週間前は新しいことをせず、今までの復習に集中
【3ヶ月プラン(短期集中)】
より短期間で合格を目指す場合は、毎日2〜3時間の学習時間を確保し、上記のスケジュールを凝縮します。
章別の学習ポイント
第1章:医薬品に共通する特性と基本的な知識
- 重要度:★★★(基礎だが重要)
- 学習のコツ:医薬品の副作用、相互作用、適切な使用方法など、すべての章の基礎となる内容。最初にしっかり理解しましょう。
第2章:人体の働きと医薬品
- 重要度:★★★★(理解が必要)
- 学習のコツ:暗記だけでなく、体の仕組みを理解することが重要。図やイラストを活用して視覚的に覚えましょう。
- 頻出分野:消化器系、呼吸器系、循環器系、神経系
第3章:主な医薬品とその作用
- 重要度:★★★★★(最重要・最難関)
- 出題数:40問(全体の1/3)
- 学習のコツ:
- 成分名と効能効果をセットで覚える
- 副作用や使用してはいけない人(禁忌)を重点的に
- 似た成分を比較しながら覚える
- 実際に店舗で医薬品を見て覚えるのも効果的
- 頻出分野:かぜ薬、解熱鎮痛薬、胃腸薬、眼科用薬、皮膚用薬
第4章:薬事関係法規・制度
- 重要度:★★★(暗記中心)
- 学習のコツ:法律の条文をそのまま覚えるのは大変。重要ポイントを絞って効率的に暗記しましょう。
- 頻出分野:医薬品の分類、販売方法、店舗の管理、登録販売者の義務
第5章:医薬品の適正使用・安全対策
- 重要度:★★★(実務的)
- 学習のコツ:添付文書の読み方、副作用報告制度など、実務に直結する内容。実際の添付文書を見ながら学習すると理解が深まります。
効率的に覚えるための5つのテクニック
1. アウトプット中心の学習
テキストを読むだけでなく、問題を解いて知識を定着させましょう。インプット3割、アウトプット7割が理想です。
2. 語呂合わせ・イメージ記憶
覚えにくい成分名や効能は、語呂合わせやイメージで記憶すると忘れにくくなります。
3. 実物を見て覚える
ドラッグストアで実際の医薬品パッケージを見ることで、視覚的に記憶に残りやすくなります。
4. 関連付けて覚える
バラバラに覚えるのではなく、「この症状にはこの成分」「この成分はこの副作用」と関連付けて覚えましょう。
5. 毎日少しずつ継続
1日10時間勉強するより、毎日2時間を継続する方が記憶は定着します。
試験直前1週間の過ごし方
- 新しいことは覚えない:今まで勉強したことの総復習に専念
- 苦手分野の最終確認:間違えやすいポイントをチェック
- 暗記事項の最終確認:成分名、副作用、法規など
- 体調管理を最優先:睡眠をしっかり取り、無理をしない
- 試験当日のシミュレーション:持ち物確認、会場までのルート確認
登録販売者のリアルな働き方と給与事情
勤務時間と働き方
【ドラッグストアの場合】
- 勤務時間:シフト制(早番・遅番など)9:00〜22:00の間で実働8時間
- 休日:シフト制で週休2日
- 残業:店舗により異なるが、月10〜20時間程度
- 特徴:幅広い医薬品を扱え、キャリアアップしやすい
【調剤薬局・薬店の場合】
- 勤務時間:9:00〜18:00前後(定時退勤しやすい)
- 休日:日曜・祝日、平日1日(水曜や木曜が多い)
- 残業:比較的少なめ
- 特徴:地域密着型で長期的な信頼関係を築ける
【パート・アルバイトの場合】
- 勤務時間:週2〜3日、1日4〜6時間など柔軟に対応可能
- 子育て中の方、ダブルワークの方にも人気
給与相場(2024年現在)
【正社員の場合】
- 初任給:月給20万円〜25万円
- 経験者:月給25万円〜35万円
- 店舗管理者・店長クラス:月給30万円〜45万円
- 年収:300万円〜500万円程度
- ※資格手当(月3,000円〜20,000円)が別途支給される企業が多い
【パート・アルバイトの場合】
- 時給:1,000円〜1,500円
- 資格保有者:時給1,200円〜1,800円
- ※無資格者より時給200〜300円高い傾向
【派遣社員の場合】
- 時給:1,400円〜2,000円
- ※比較的高時給で、様々な職場を経験できる
大手ドラッグストアチェーンの待遇例
- マツモトキヨシ、ウエルシア、ツルハドラッグ、スギ薬局などの大手では、資格手当、昇給制度、賞与、社会保険完備、社員割引など充実した待遇が期待できます。
実際の声:登録販売者として働く人たちの体験談
Aさん(20代女性・ドラッグストア勤務) 「未経験から登録販売者資格を取得して就職しました。お客様から『あなたに相談してよかった』と言われると、本当に嬉しいです。最初は覚えることが多くて大変でしたが、今では店舗管理者候補として育成を受けています」
Bさん(30代男性・調剤薬局勤務) 「前職は営業職でしたが、キャリアチェンジで登録販売者に。年収は少し下がりましたが、残業が減り、家族との時間が増えました。地域のお客様と長くお付き合いできるのが魅力です」
Cさん(40代女性・パート勤務) 「子育てとの両立を考えてパートで週3日働いています。資格があるおかげで時給が高く、短時間でも十分な収入になります。ブランクがあっても復帰しやすい資格だと実感しています」
Dさん(50代男性・店長) 「登録販売者として10年のキャリアを積み、現在は店長として店舗全体をマネジメントしています。医薬品の知識だけでなく、経営的な視点も求められ、やりがいがあります」
登録販売者に向いている人・求められるスキル
こんな人が登録販売者に向いています
1. 人と接することが好きな人
お客様との会話を通じて症状を聞き出し、適切な医薬品を提案する仕事です。コミュニケーション能力が活かせます。
2. 健康や医薬品に興味がある人
「この成分はどう効くのか」「体の仕組みはどうなっているのか」といった探究心がある方は、学習も楽しく続けられます。
3. 人の役に立ちたいという気持ちがある人
「お客様の困りごとを解決したい」「健康をサポートしたい」という奉仕の気持ちが、この仕事の原動力になります。
4. 学び続ける姿勢がある人
医薬品や健康に関する情報は常にアップデートされます。新しい知識を学び続ける意欲が大切です。
5. 責任感がある人
医薬品は人の健康に直結します。「この薬で大丈夫だろうか」と常に慎重に考え、責任を持って対応できる方が向いています。
求められる基本スキル
- コミュニケーション能力:お客様の話をよく聞き、分かりやすく説明する
- 観察力・ヒアリング力:お客様の様子から症状を読み取る
- 判断力:医療機関の受診を勧めるべきか、医薬品で対応できるかを判断
- 記憶力:多数の医薬品の成分や効能を覚える
- パソコンスキル:在庫管理、発注などで基本的なPC操作が必要
これらは特別な才能ではなく、学習や経験を通じて身につけられるものばかりです。
よくある質問(Q&A)
Q1. 登録販売者に年齢制限はありますか?
A. 年齢制限は一切ありません。高校生から60代、70代まで幅広い年齢層の方が合格しています。実際、40代・50代から資格を取得して活躍している方も多数います。
Q2. 理系の知識がなくても大丈夫ですか?
A. 大丈夫です。文系出身の方も多く合格しています。人体や医薬品の知識は、試験に必要な範囲を学べば十分です。化学式などの専門的な知識はほとんど出題されません。
Q3. 資格取得にどれくらいの期間がかかりますか?
A. 学習方法や1日の勉強時間によりますが、一般的に3〜6ヶ月程度です。毎日2時間勉強すれば、3〜4ヶ月で合格レベルに到達できます。
Q4. 一度不合格でも再受験できますか?
A. もちろんです。何度でも受験できます。不合格だった場合、次回試験に向けて弱点を克服して再チャレンジしましょう。
Q5. 薬剤師との違いは何ですか?
A. 薬剤師は大学の薬学部(6年制)を卒業して国家試験に合格する必要がある上位資格です。処方箋に基づく調剤や、第1類医薬品の販売ができます。一方、登録販売者は第2類・第3類医薬品の販売ができ、受験資格に学歴や実務経験が不要です。
Q6. 合格後すぐに店舗管理者になれますか?
A. 合格直後は「研修中」の扱いとなり、店舗管理者にはなれません。過去5年間で通算2年以上かつ1,920時間以上の実務経験を積むことで、「店舗管理者」になれます。
Q7. ネット販売の会社でも働けますか?
A. はい、働けます。オンラインでの医薬品販売が拡大しており、ECサイト運営企業での登録販売者の求人も増えています。チャットやメールでのお客様対応、商品説明の作成などが主な業務です。
Q8. 実務経験がなくても就職できますか?
A. 資格があれば未経験でも就職可能です。ただし、「研修中」の期間(実務経験2年未満)は、薬剤師や実務経験のある登録販売者の管理・指導のもとで働く必要があります。
Q9. 複数の都道府県で受験できますか?
A. はい、できます。各都道府県ブロックで試験日が異なるため、複数のブロックで受験することで合格のチャンスを増やせます。
Q10. 登録販売者の資格に更新は必要ですか?
A. 資格自体に更新はありませんが、年に1回以上の外部研修受講が義務付けられています(各都道府県が実施)。常に最新の知識をアップデートすることが求められます。
合格から就職までのロードマップ
ステップ1:情報収集・学習計画(1〜2週間)
- 登録販売者の仕事内容を理解する
- 試験日程・試験会場を確認する
- 学習方法を決定する(独学・通信・通学)
- 教材を揃える
- 学習スケジュールを立てる(試験日から逆算)
ステップ2:学習開始(3〜6ヶ月)
- テキストで基礎知識を習得
- 章ごとに理解を深める(特に第3章を重点的に)
- 過去問題を繰り返し解く
- 模擬試験で実力チェック
- 苦手分野を集中的に克服
ステップ3:試験申込・受験(試験1〜2ヶ月前)
- 受験する都道府県の薬務課で申込手続き
- 受験票が届いたら試験会場を確認
- 試験直前1週間は総復習に集中
- 体調を整えて試験当日を迎える
ステップ4:合格発表・販売従事登録
- 合格発表(試験の約1ヶ月後)
- 合格証書が届く
- 重要:就業先の店舗がある都道府県で「販売従事登録」が必要
- この登録をして初めて登録販売者として働けます
- 登録には申請書、合格証書、写真などが必要
ステップ5:就職活動
- 求人サイト、ハローワーク、企業の採用サイトで求人を探す
- 希望する勤務形態・勤務地・企業を選ぶ
- 履歴書・職務経歴書を作成(資格欄に登録販売者を記載)
- 面接対策(志望動機、登録販売者を目指した理由を明確に)
ステップ6:面接・内定
- 明るく元気な対応を心がける
- なぜ登録販売者を目指したのか、具体的に説明
- お客様の健康をサポートしたい気持ちをアピール
- 学び続ける意欲を伝える
ステップ7:入職・実務スタート
- 研修期間(1〜3ヶ月)で基本業務を学ぶ
- 先輩の指導のもと、接客・医薬品販売を経験
- 分からないことは積極的に質問
- 2年間の実務経験を積んで店舗管理者を目指す



ポイント:焦らず、一歩ずつ着実に進むことが大切です。合格後もキャリアは続きます。
登録販売者資格取得を成功させる7つの秘訣
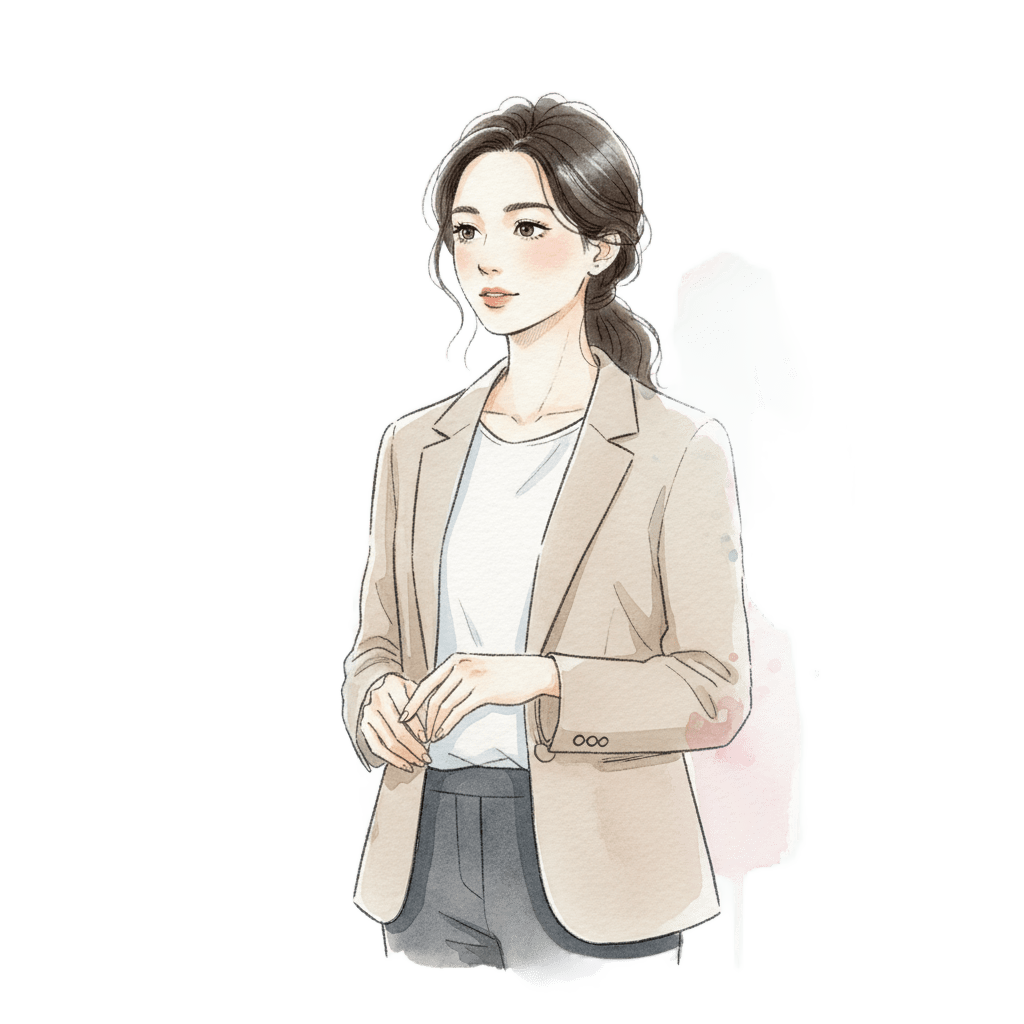
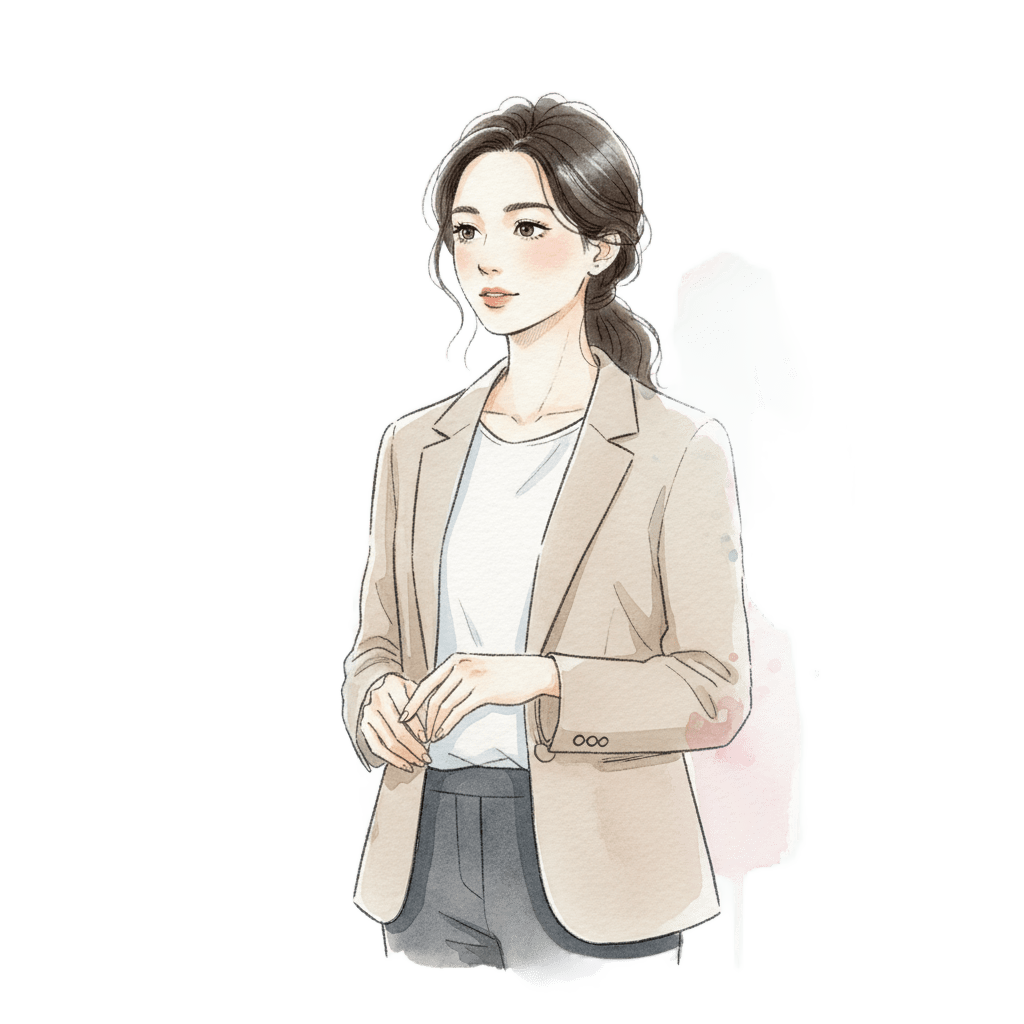
1. 明確な目標とモチベーションを持つ
「なぜ登録販売者になりたいのか」「資格を取ってどうなりたいのか」を明確にしましょう。目標が明確だと、勉強のモチベーションが続きます。
「地域の人の健康をサポートしたい」「安定した仕事に就きたい」「専門知識を身につけたい」など、あなたの理由を書き出してみましょう。
2. 学習スケジュールを立てて習慣化する
「毎朝6時から1時間」「通勤時間に30分」など、具体的に学習時間を決めて習慣化することが継続の秘訣です。
3. 完璧主義にならない
100%理解してから次に進もうとすると挫折しやすくなります。7〜8割理解したら次に進み、繰り返し学習で定着させる方が効果的です。
4. アウトプット重視の学習
テキストを読むだけでなく、問題を解く、人に説明する、ノートにまとめるなど、アウトプットすることで記憶が定着します。
5. 実物に触れて学ぶ
ドラッグストアで実際の医薬品を見ることで、パッケージや成分表示が視覚的に記憶に残ります。「この薬はあの棚にあったな」と思い出しやすくなります。
6. 過去問を徹底的に解く
過去問は最高の教材です。3〜5年分を最低3回は繰り返し解きましょう。出題傾向が分かり、自分の弱点も明確になります。
7. 体調管理も勉強のうち
睡眠不足や体調不良では学習効率が下がります。適度な休息を取り、無理なく続けることが合格への近道です。
登録販売者からのキャリアパス
登録販売者として働き始めた後も、様々なキャリアパスが開けています。
キャリアアップの道
【店舗スタッフ】(実務経験0〜2年) ↓ 【店舗管理者】(実務経験2年以上)
- 薬剤師がいない店舗で医薬品販売の責任者になれる
- 資格手当がさらに増額される企業も ↓ 【副店長・店長】(実務経験5年前後)
- 店舗全体のマネジメント
- スタッフの育成、売上管理 ↓ 【エリアマネージャー】(実務経験10年前後)
- 複数店舗を統括
- 新店舗の立ち上げ ↓ 【本部スタッフ】
- 商品開発・バイヤー
- 教育・研修担当
- 薬事関連業務
横展開のキャリア
- 登録販売者講師:スクールや企業で後進を育成
- 医薬品メーカー営業:医薬品の知識を活かした営業職
- 医療・健康系ライター:医薬品や健康に関する記事執筆
- 独立開業:薬店を開業(店舗管理者の要件を満たせば可能)
ダブルライセンスでさらにキャリアアップ
登録販売者の資格にプラスして、以下の資格を取得することで、さらに専門性が高まります。
- 調剤薬局事務:調剤薬局での活躍の場が広がる
- 医療事務:医療機関での就業も視野に
- 薬膳コーディネーター:東洋医学の知識もプラス
- サプリメントアドバイザー:健康食品の提案力向上
- ビューティーアドバイザー:美容と健康の両面からアドバイス
まとめ:登録販売者は未来への確かな一歩
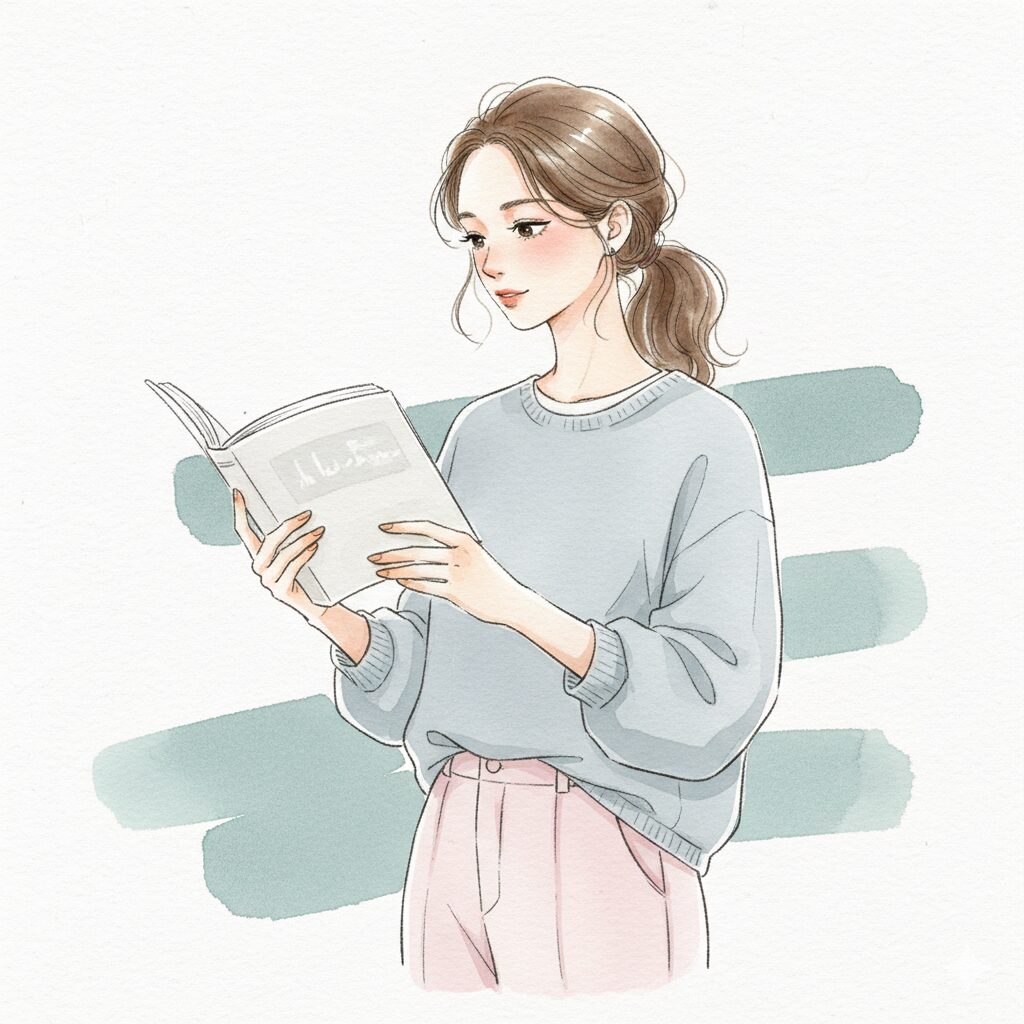
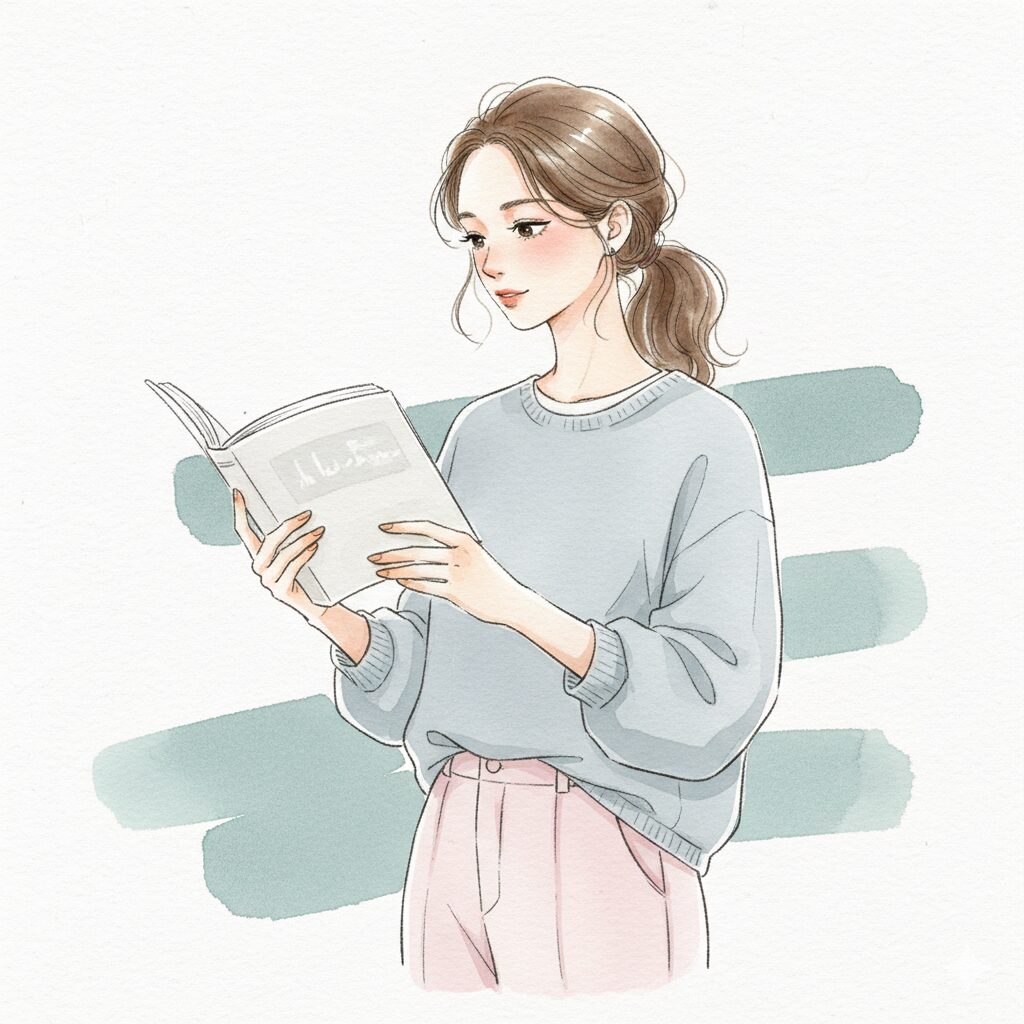
登録販売者は、安定性、将来性、社会貢献性を兼ね備えた、とても魅力的な国家資格です。
- 誰でも受験できる国家資格:学歴・実務経験不問
- 全国どこでも働ける:求人が豊富で就職率が高い
- ライフステージに合わせて働き方を選べる:正社員・パート・派遣など
- 年齢を重ねても活躍できる:長期的なキャリア展望
- 人の役に立てる:お客様の健康をサポートする社会的意義
「薬に興味がある」「人と接する仕事がしたい」「専門的なスキルを身につけたい」
そう考えているなら、登録販売者という選択肢をぜひ検討してみてください。
一度学んだ知識とスキルは、あなたの一生の財産になります。
まずは気軽に、登録販売者について調べてみる、通信講座の資料請求をしてみる、ドラッグストアで働く登録販売者の方に話を聞いてみる…どんな小さな一歩でも構いません。
あなたの「やってみたい」という気持ちを、ぜひ行動に変えてみてください。
お客様から「ありがとう」と言われるやりがいのある毎日、安定した収入、専門家としての自信、そして何より「自分の力で人の役に立てている」という誇り。
登録販売者の世界は、それらすべてを手に入れるチャンスを、あなたに差し出しています。



新しいキャリアへの第一歩を、心から応援しています!
【参考リンク集】
公式情報
- 厚生労働省 登録販売者試験について
- 各都道府県の薬務課
- 試験日程・申込方法は各都道府県で確認してください
主要な通信講座
求人情報
- ハローワークインターネットサービス
- Indeed、求人ボックス、マイナビ、リクナビなどの求人検索サイト
- 各ドラッグストアチェーンの採用サイト
おすすめ書籍
- 『7日間でうかる! 登録販売者 テキスト&問題集』(KADOKAWA)
- 『ユーキャンの登録販売者 速習テキスト&重要過去問題集』(U-CAN)
- 『登録販売者 合格教本』(中央法規出版)
医薬品情報
- 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)
- 一般用医薬品の添付文書・情報が検索できます



この記事が、あなたの新しいキャリアの第一歩になることを願っています。頑張ってください!
最終更新:2025年10月(試験情報や制度は変更される場合があります。最新情報は各都道府県の公式サイトでご確認ください)