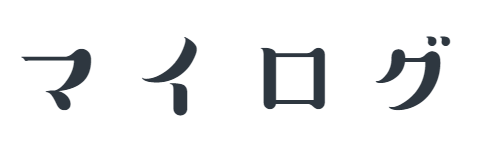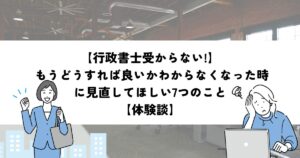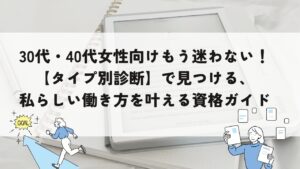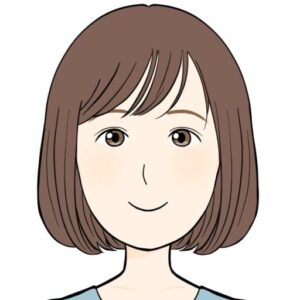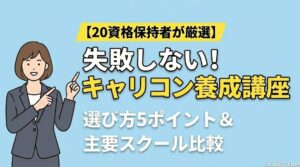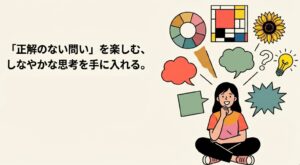ブログ案内犬しろちゃん
ブログ案内犬しろちゃん、「いっそのこと、先に社労士事務所に転職しちゃおうかな?」「実務を経験しながら勉強したら、合格に近づけるかも?」



こんにちは!資格好き主婦ライターのまいです。
社労士試験の勉強、本当にお疲れ様です! 勉強を進める中で、先に社労士事務所に転職しちゃおうかな?その方が合格に近づけるかも?なんて考えたことはありませんか?
でも、同時にこんな不安もよぎりますよね。
- 「そもそも未経験の受験生でも雇ってくれる事務所なんてあるの?」
- 「働きながら勉強時間って、ちゃんと確保できるのかな…」
- 「今の会社よりお給料が下がったらどうしよう…」
私も社労士受験生時代に、2年間社労士法人で補助者として働いていた経験があるので、その気持ち、すごくよく分かります。
結論から言うと、「社労士受験生が社労士事務所で働くのはアリ!でも、事務所選びとお給料の条件はしっかり確認してね!」 です。



この記事では、私の実体験も踏まえながら、社労士受験生が補助者として働くことのリアルな実態、メリット・デメリット、そして後悔しないための事務所選びのポイントまで、詳しくお伝えしていきます。
この記事を読めば、あなたが「社労士事務所への転職」という選択肢を冷静に判断できるようになりますよ!



こんにちは!
資格好きライターのまい(@maisawaco)です。
行政書士、宅建、FP、カラーコーディネーター、簿記3級、ビジネス実務法務検定2級など15種類の資格を持つ資格好き。
学生時代の偏差値40台、主婦の立場から、記事寄稿やブログなどで資格試験のノウハウを発信しています。
社労士事務所の求人、受験生・未経験でも見つかる?


まず気になるのが、「そもそも求人はあるの?」という点ですよね。
2.1 都市部と地方での求人数の違い
社労士補助者の求人は、都市部の方が多い傾向 にあります。企業が多い地域には、それだけ社労士事務所も多く存在するためです。
一方、地方でも、県庁所在地や比較的大きな市であれば、社労士法人などが複数存在し、通年で求人が出ている可能性 があります。私が住んでいる地域も地方ですが、常にいくつかの求人は見かけました。



他の中小企業と同じく、社労士事務所も人手不足です。ある程度の都市なら、複数の事務所がどこかしら通年で人材を募集しています



まずは、お住まいの地域の求人サイトやハローワークなどで、「社労士補助」「社労士事務所 事務」といったキーワードで検索してみましょう。
個人事務所 vs 社労士法人:求人の特徴


求人を探す際には、事務所の規模にも注目してみましょう。
- 個人事務所
所長先生と補助者数名(ご家族の場合も)といった小規模な体制が多く、求人が出る頻度は低めかもしれません。 ただ、アットホームな雰囲気で、先生との距離が近いというメリットも考えられます。 - 社労士法人(中~大規模): 補助者の人数も多く、パートの方や主婦の方も活躍しているケースが多いです。[7, 8] そのため、人の入れ替わりや事業拡大に伴う増員などで、定期的に求人が出やすい傾向 にあります。[8]
どちらが良いかは一概には言えませんが、求人の探しやすさで言えば、社労士法人の方が見つけやすいかもしれません。
「受験生歓迎」の求人を見つけるポイント
求人票をよく見ると、「社労士試験の勉強中の方、歓迎」「資格取得を目指している方、応援します」といった記載がある求人も少なくありません。
こうした事務所は、将来的に資格を取得し、事務所の中心メンバーとして活躍してくれること を期待して、受験生を採用するケースが多いです。



多少教育コストがかかっても、やる気のある受験生が社労士先生になることは、事務所にとってもおおきなメリットがあります。
・「仕事内容」や「求める人材」欄に、「受験生歓迎」「勉強中の方尚可」などの記載があるか
・「資格取得支援制度」や「試験前の休暇制度」など、勉強への配慮があるか
・未経験者向けの研修制度が整っているか
面接の際に、「現在、社労士試験の勉強をしているのですが、働きながら勉強時間を確保することは可能でしょうか?」と正直に質問してみるのも良いでしょう。



事務所の反応で、受験生への理解度がある程度測れます。



今の会社の顧問社労士さんの事務所は、独立に際しお客さんを数件持って行って良いなど、すごく寛容です。そんな社労士事務所もありますよ!
社労士補助者のリアルな仕事内容とは?
では、実際に社労士補助者として採用された場合、どんな仕事をするのでしょうか?
メインは社会保険・労働保険の手続き業務
社労士補助者の主な仕事は、いわゆる「1号業務」と呼ばれる手続き関係 が中心です。
- 社会保険(健康保険・厚生年金)の加入・喪失手続き
- 労働保険(雇用保険・労災保険)の加入・喪失手続き
- 雇用保険の各種給付金(傷病手当金、出産手当金など)の申請
- 労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の作成
- その他、帳簿書類の作成、給与計算補助、電話・来客応対など
基本的には、社労士の先生の指示のもと、これらの書類作成や電子申請、役所への提出などを行います。



給与計算や企業への訪問など、すべての業務に携わらせてくれる事務所も多いです!
未経験でも大丈夫?求められるスキル
「未経験だけど、専門的な手続きなんてできるかな…」と不安に思うかもしれません。
もちろん、入社後に覚えることはたくさんありますが、多くの事務所では、未経験者向けの研修やOJT(実務を通じた指導) が用意されています。
ただし、どんな事務所でも共通して求められるのは「即戦力」 になろうとする意欲です。特に小規模な事務所では、一人ひとりが効率よく業務をこなすことが期待されます。



未経験であっても、以下のようなスキルや経験はアピールポイントになります。
- 基本的なPCスキル(Word、Excelは必須レベル)
- 一般事務や経理、総務などの実務経験
- コミュニケーション能力(電話応対や顧客とのやり取りで重要)
- 簿記やFPなど、関連する資格
- そして何より、「社労士の勉強をしている」という知識と意欲!
社労士の勉強で得た知識は、間違いなく業務理解の助けになります。
実務経験が受験勉強の強力な武器になる理由
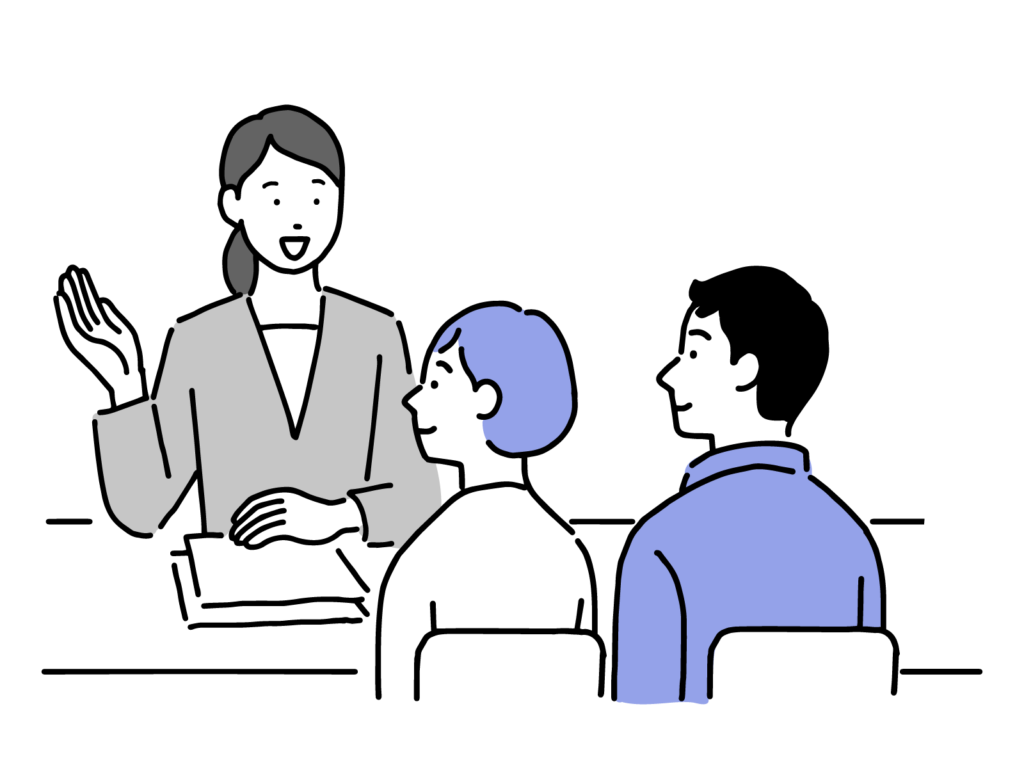
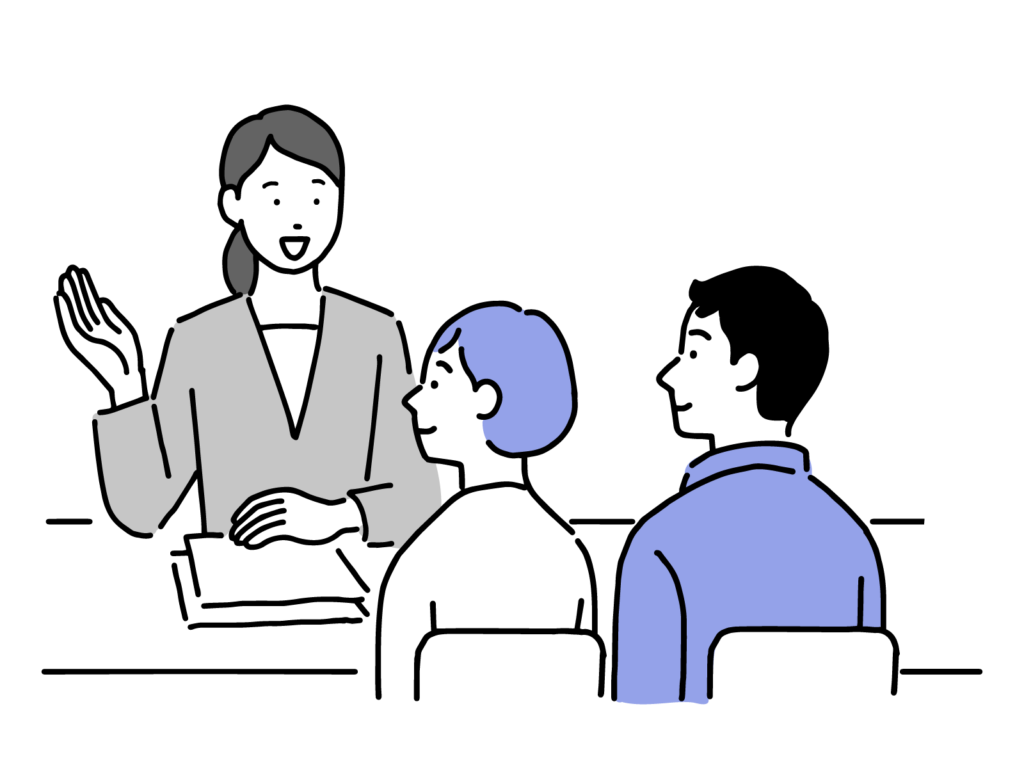
社労士補助者として働く最大のメリットの一つが、実務を通して試験範囲の知識が深まること です。
テキストで学んだ手続きが、実際の業務でどのように行われるのかを目の当たりにすることで、知識が立体的になり、記憶に定着しやすく なります
- 雇用保険の加入手続きをすれば、「適用事業所」「被保険者資格取得届」といったキーワードがスッと頭に入ってくる。
- 労災の申請書類を作成すれば、「業務災害」「通勤災害」の違いや給付内容がリアルに理解できる。
- 様々な企業の事例に触れることで、年金や助成金など、幅広い知識が自然と身につく。
「これは試験に出るやつだ!」と意識しながら業務に取り組むことで、日々の仕事がそのまま受験勉強の一部 になります。実務経験がある分野は、問題を解くスピードも格段に上がりますよ!
【一番気になる】勉強時間は確保できる?給料は?


実務経験が勉強に役立つとはいえ、合格のためにはまとまった勉強時間の確保が不可欠です。そして、生活していくためにはお給料も重要ですよね。
勉強時間確保のリアル:事務所の理解がカギ
正直にお伝えすると、勉強時間をしっかり確保できるかどうかは、事務所によるところが大きい です。
「受験生を応援します!」と言ってくれる事務所でも、繁忙期には残業が続いたり、日々の業務で疲れてしまって、帰宅後に勉強する気力が湧かない…なんてことも。



これは私の反省点でもあるのですが、私は補助者時代、業務に追われてしまい、思うように勉強時間を確保できませんでした…(同期入社の方は、家事と両立しながら見事合格されましたが!)。
- 残業時間の実態: 面接で聞きにくい場合は、転職口コミサイトなども参考に。
- 試験前の休暇制度: 具体的にどのくらいの期間、休暇が取れるのか。
- 資格取得支援: 受験費用補助や合格祝い金などがあると、モチベーションに繋がります。
- 所員の雰囲気: 資格取得を目指している先輩がいるか、勉強に対して協力的な雰囲気か。
「定時で帰って、しっかり勉強時間を確保したい」という希望があるなら、その点を面接で明確に伝え、理解のある事務所を選ぶことが何よりも重要です。



合格した同期の方は、9:30~15:30のパートで、残業も極力していませんでした
給料・待遇の実態:パート採用が多い?正社員からの転職は要注意
社労士補助者の求人は、パートタイムでの募集も多い のが実情です。時給制で、フルタイムで働いたとしても、正社員の給与水準には届かないケースが一般的です。
私の場合は時給1,100円で、地域的には悪くない条件でしたが、やはり正社員時代の収入と比べると下がりました。
そのため、現在正社員として働いていて、給与面に大きな不満がないのであれば、個人的には資格取得後の転職をおすすめします。
社労士資格があれば、正社員として採用される可能性が高まりますし、待遇面でも有利になることが多いです。(ただし、駆け出しの頃は前職より給与が下がる可能性も覚悟しておきましょう)
一方で、
- 現在パートやアルバイトで働いている
- 今の仕事内容や環境に大きな不満がある
- 実務経験を積んで、早く社労士登録をしたい
といった方にとっては、受験生のうちに補助者として働くことは、魅力的な選択肢になるでしょう。



資格未取得でも高待遇での募集があれば、検討する価値アリ。ぜひチェックしてみてください!
【体験談】元補助者(私)の一日のスケジュール
参考までに、私が入社1年目だった頃の一日の流れをご紹介しますね。



需要はあるのかな?
- 7:30 家を出発(電車通勤40分)
- 8:00 早めに着いた日は、カフェで勉強タイム(理想…現実はあまりできず)
- 9:00 出社、1日のスケジュール確認、メールチェック、顧問先との連絡
- 9:30 チームミーティング(進捗確認、情報共有)
- 10:00手続き書類作成(メイン業務)、役所への外出など
- 繁忙期(年度更新、算定基礎届の時期)は、ひたすら書類作成![10]
- 12:00 お昼休憩(お弁当持参。勉強する雰囲気ではなかった…)
- 13:00 社労士の先生に同行して顧問先訪問(手続き書類の説明や返却など)
- 15:00 帰社後、再び書類作成。顧問先からの電話問い合わせ対応など
- 17:30 業務の振り返り、翌日の予定調整
- 18:00 終業(定時で帰れる日もあれば、残業の日も半々くらい…)
- 18:40 帰宅(残業の日は20時~22時頃)
- 19:20 夕食(週末の作り置きが大活躍)
- 21:30 勉強タイム(…のはずが、疲れてテレビを見てしまう日も多々)
- 23:00 就寝



今振り返ると、もう少しうまく時間を使えたはず…と反省しています(笑)。皆さんは私を反面教師にしてくださいね!
社労士受験生が補助者として働くメリット・デメリットまとめ
ここまでお伝えしてきた内容を、メリット・デメリットとして整理してみましょう。
メリット
- 実務経験が積める
試験勉強の理解が深まり、知識が定着しやすくなる。 - 合格後の登録要件
社労士登録に必要な「2年以上の実務経験」にカウントされる。(※実務従事期間の証明が必要です) - モチベーション維持
実際に社労士が活躍する姿を間近で見たり、顧客から感謝されたりすることで、勉強への意欲が高まる。 - 合格後の就職に有利
実務経験があれば、資格取得後の就職・転職活動をスムーズに進められる可能性がある。
デメリット
- 勉強時間の確保が難しい可能性
業務量や事務所の雰囲気によっては、十分な勉強時間を確保できない場合がある。 - 給料ダウンの可能性
特に正社員からの転職の場合、収入が減ることが多い。 - 事務所との相性
事務所の方針や人間関係が合わないと、ストレスを感じてしまう可能性も。 - 業務と勉強の両立による疲労
仕事で疲れてしまい、勉強への意欲が削がれてしまうリスクがある。(←私のことです…)
後悔しないために!事務所選びで絶対に確認すべきこと
もし補助者として働くことを決めたなら、「事務所選び」 が何よりも重要です。入社してから「こんなはずじゃなかった…」とならないために、以下の点は必ず確認しましょう。
- 受験生への理解と配慮:
- 勉強時間の確保(定時退社、試験休暇など)について、具体的な制度や実績があるか?
- 資格取得を応援する雰囲気があるか?(面接での質問や所員の様子から判断)
- 業務内容と教育体制:
- 具体的にどのような業務を担当するのか?
- 未経験者向けの研修やOJTはしっかりしているか?
- 質問しやすい環境か?
- 労働条件と待遇:
- 給与、賞与、昇給の見込みは?
- 残業時間の実態は?(固定残業代が含まれていないかもチェック)
- 社会保険への加入など、福利厚生は整っているか?
- 事務所の雰囲気:
- 所員同士のコミュニケーションは円滑か?
- 事務所全体の忙しさや空気感は自分に合っているか?(可能であれば職場見学をさせてもらうのも◎)



焦って決めずに、複数の事務所を比較検討し、自分が納得できる条件の事務所 を見つけることが大切です。
働きながらの転職活動、一人で悩んでいませんか?
「自分に合った社労士事務所を見つけたいけど、どう探せばいいんだろう…」 「勉強時間を確保できるか、面接でちゃんと確認できるか不安…」 「そもそも未経験の自分を採用してくれる事務所って本当にあるの?」
社労士試験の勉強だけでも大変なのに、働きながらの転職活動はさらに負担が大きいですよね。
そんなあなたには、士業・管理部門に特化した転職エージェント「ヒュープロ」 の活用がおすすめです。


ヒュープロは、社労士事務所や企業の法務・経理部門との太いパイプを持ち、業界最大級の求人数(全国9,000件以上!) を誇ります。
- 業界知識が豊富なキャリアアドバイザー が、あなたの経験や希望(もちろん「勉強時間」の希望も!)を丁寧にヒアリング。
- 大量の求人メールを送るのではなく、あなたに本当にマッチした求人のみを厳選してスピーディーに紹介 してくれます。
- 応募書類の添削や、合格率を上げるための面接対策 も無料でサポート!
- 一般には公開されていない**「非公開求人」** に出会えるチャンスも!
「忙しくて転職活動に時間を割けない」「自分に合う求人だけ効率よく知りたい」というあなたにぴったりのサービスです。



まずは無料相談から。可能性を広げてみませんか?
\▼ 登録・相談は無料!社労士受験生歓迎の求人も多数!▼
将来社労士を目指すなら、選択肢の一つとして検討する価値あり
社労士受験生が補助者として社労士事務所で働くことは、実務経験を積みながら合格を目指せるという大きなメリット があります。特に、実務経験がそのまま勉強に直結するのは、他の資格にはない魅力かもしれません。



ただし、勉強時間の確保や給与面でのデメリット も考慮する必要があります。
勢いで転職するのではなく、ご自身の状況(現在の仕事、経済状況、学習の進捗度など)と、将来どのような社労士になりたいかをよく考えた上で、慎重に判断することが大切です。



もし、「この求人、良さそうかも!」と思える事務所が見つかったら、まずは話を聞いてみることから始めてみてはいかがでしょうか?
この記事が、あなたのキャリア選択の一助となれば幸いです。応援しています!