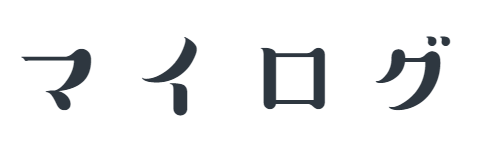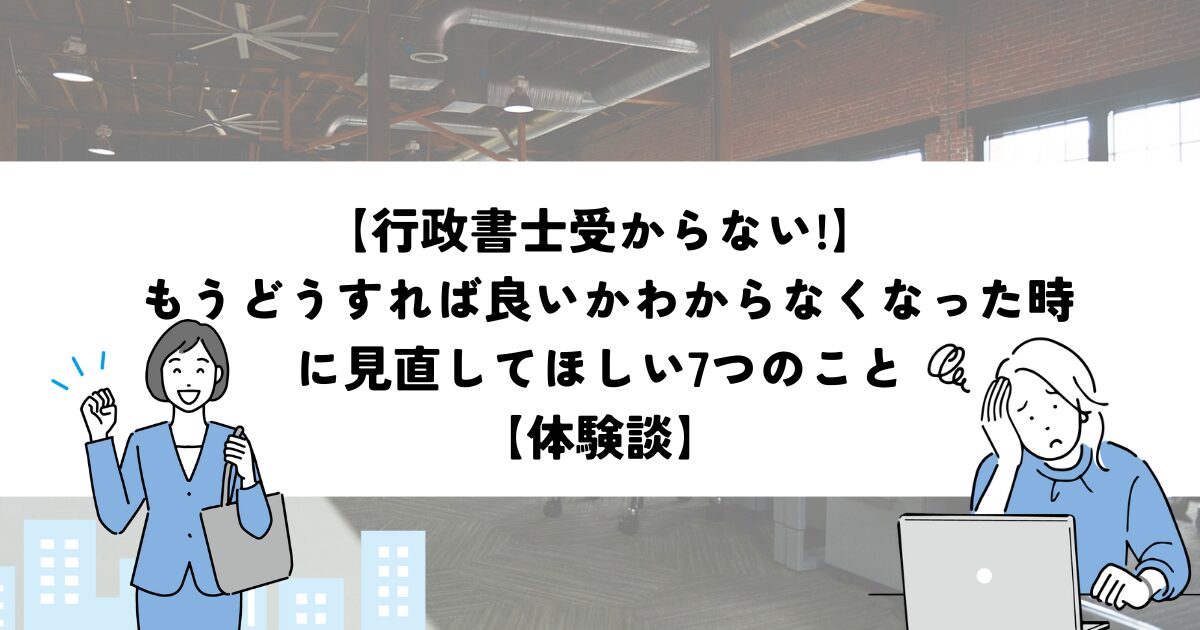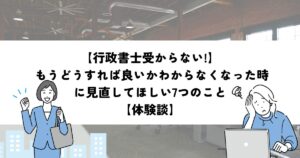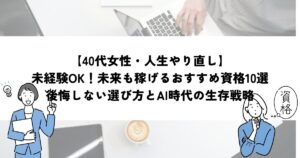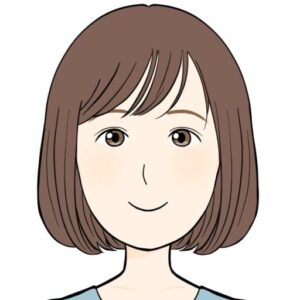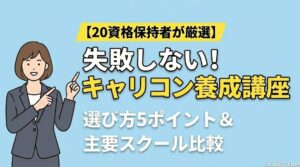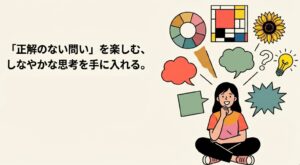ブログ案内犬しろちゃん
ブログ案内犬しろちゃん「行政書士試験、何度受けても受からない…もう無理かもしれない…」
そんな風に、合格通知を手にできない現実を前に、心が折れそうになっていませんか?
何を隠そう、このブログを書いている私も、行政書士試験には3回目の挑戦でやっと合格した経験があります。不合格通知を見るたびに、「やる気が少なすぎる!」「勉強法が間違っているのかな」と、出口の見えないトンネルの中にいるような気持ちでした。



でも、諦めずに試行錯誤を重ねた結果、合格を掴み取ることができました。
今回は、かつての私と同じように「行政書士に受からない!」と悩み、どうすれば良いかわからなくなってしまったあなたへ向けて、合格のために見直してほしい勉強法のポイントを、私の体験談を交えながら具体的にお伝えします。
この記事を読めば、きっとあなたの勉強の「どこ」を改善すれば良いのかが見えてくるはずです。諦めるのはまだ早い! 一緒に合格への道筋を見つけましょう。
- 行政書士試験に「受からない」人が見直すべき勉強法の7つのポイント
- 3回目で合格した筆者のリアルな失敗談と改善策
- 非効率な勉強から脱却し、合格に近づくための具体的なヒント



こんにちは!資格好き主婦のまい(@maisawaco)です。
私は行政書士、宅建、FP、カラーコーディネーター、簿記3級、ビジネス実務法務検定2級など21個の資格を持つ資格好き。
学生時代の偏差値40台、主婦の立場から、記事寄稿やブログなどで資格試験のノウハウを発信しています。
行政書士にどうしても受かりたいなら、まずは「勉強法」を見直そう


「頑張っているのに結果が出ない…」その原因は、努力の方向性が間違っているだけかもしれません。
行政書士試験は決して簡単な試験ではありませんが、正しい方法で、必要な量の学習を積み重ねれば、必ず合格できる試験です。
「受からない」と嘆く前に、まずは勉強法を客観的に振り返ってみませんか? 基本に立ち返り、非効率になっている部分を見つけることが、合格への最短ルートになるはずです。
【体験談】私が陥ったワナと見直しポイント7選


ここからは、私が実際に「受からない…」と悩んでいた時に見直したポイントを7つご紹介します。「あ、これ自分もやってるかも…」と思う部分がないか、チェックしてみてくださいね。
行き当たりばったり?学習スケジュールはちゃんと守れていますか?
意外と多いのが、明確な学習計画を立てていない、または立てても守れていないケースです。
どこをいつまでに終わらせるという学習計画が立てられていない、もしくはスケジュールを立てても守れていないので、最後の方で時間が足りずにアウトプット、記述対策、一般教養対策がおろそかになり、思ったように点数が取れなくなってしまうのです。
【私の失敗談】 最初の年は、「とりあえず行政法から始めよう!」と意気込んだものの、具体的な期限を決めずに進めてしまい、気づけば行政法ばかりに時間をかけすぎていました…。



ほかと比べて比較的簡単といわれている行政法ばっかりやってどうするのー!



結果、民法法や他の科目の対策が不十分なまま本番を迎えることに。当然、結果は伴いませんでした。
【改善策】
- ゴール(試験日)から逆算して計画を立てる
全科目を最低2周、できれば3周できるスケジュールを組みましょう。特に、8月終わり頃からは過去問演習や記述式対策など、アウトプット中心の学習に切り替えられるよう、インプットはそれまでに終えるのが理想です。 - 週ごと、日ごとのタスクに落とし込む
「今週は行政法の〇〇まで進める」「今日はテキストを〇ページ読む」など、具体的な目標を設定すると、進捗管理がしやすくなります。 - 予備日を設ける
計画通りに進まないこともあります。体調不良や急用に対応できるよう、調整可能な日を設けておくと安心です。
実は全然足りてない?「勉強時間」は本当に確保できていましたか?
行政書士試験の合格に必要な勉強時間は、一般的に600時間~1000時間と言われています。もちろん個人差はありますが、この時間を一つの目安として考えてみましょう。
【私の失敗談】 私はどの試験でも、標準学習時間よりも短い時間でなんとかしようとしがちでした…。「600時間でも結構勉強した感」はあったのですが、合格した先輩の話を聞くと、やはり1000時間近く費やしたという声も多く、単純に絶対的な勉強量が足りていなかったのかもしれない、と反省しました。



宅建を50時間で合格!という実績に自信をつけ、自分をかいかぶりすぎでした。お恥ずかしい!



勉強は質×量!そして質は量をやることで向上するよ!勉強時間はやっぱり大切!
【改善策】
- 自分の学習ペースに必要な時間を把握する
過去の学習経験や現在の生活スタイルから、 realistically 確保できる時間と、合格レベルに達するために必要な時間を考えましょう。 - 短時間でも積み重ねる
平日は仕事や家事で忙しくても、「朝30分」「通勤時間に1時間」「寝る前に30分」など、スキマ時間を見つけてコツコツ積み重ねることが大切です。 - 「最小時間」で計画しない
最初からギリギリの時間設定で計画を立てると、想定外のことが起きた時に対応できません。少し余裕を持った計画を立てましょう。
それ、本当に「勉強」してた?勉強の「質」を見直そう
机に向かっている時間=勉強時間ではありません。集中して内容を理解しようとしている1時間と、テキストをただぼーっと眺めている1時間では、学習効果は全く異なります。
【私の失敗談】 恥ずかしながら、集中力が続かずカフェでぼーっとしてしまったり、ペンは動かしていても頭の中では「週末どこ行こうかな…」なんて考えていたりした時間も、勉強時間にカウントしてしまっていました…。これでは、いくら時間をかけても知識は定着しませんよね。



行政書士試験の頃はまだましで……。社労士試験を受けていた時は、心ここにあらずの時間が長かったです・・・…
【改善策】
- 時間を区切って集中する: 「ポモドーロテクニック(25分集中+5分休憩)」などを活用し、メリハリをつけて学習しましょう。
- 受動的な学習から能動的な学習へ: テキストを読むだけでなく、「これはどういう意味だろう?」「具体例を考えてみよう」「関連する過去問は?」など、常に問いかけながら学習を進めると、理解が深まります。
- 集中できる環境を作る: スマートフォンを別の部屋に置く、家族に協力をお願いするなど、勉強の妨げになるものを排除しましょう。
「やる気が出ないから…」はNG!やる気やガッツに頼る勉強法はやめよう
「合格のためには気合が必要!」「集中できないのはやる気の問題だ!」真面目な人ほど、このように精神論に頼りがちです。もちろんモチベーションは大切ですが、人間の感情には波があります。やる気に頼った勉強は不安定で、継続が難しいのです。
【私の失敗談】 「今日はなんだかやる気が出ないから、明日にしよう…」これを繰り返しているうちに、どんどん勉強が遅れていきました。モチベーションが高い時だけ頑張っても、合格レベルにはなかなか到達できません。
【改善策】
- 勉強を「習慣化」する: やる気の有無に関わらず、「決まった時間に机に向かう」「とりあえずテキストを開く」ことを毎日のルーティンにしましょう。歯磨きのように、やらないと気持ち悪い、というレベルまで持っていけると理想的です。
- ハードルを低く設定する: 最初から「毎日3時間!」と意気込むと挫折しやすいです。「まず15分だけやってみる」など、無理なく始められる目標を設定し、徐々に時間を延ばしていきましょう。
- ご褒美を設定する: 「ここまで終わったら好きなドラマを見る」「週末に美味しいものを食べる」など、小さな楽しみを用意するのも効果的です。



ぜひこちらの記事もチェックしてね
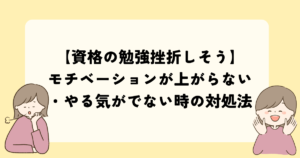
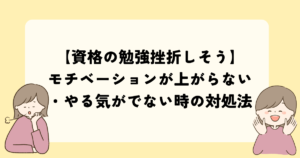
不安でつい…色々なテキストに手を出しすぎていませんか?
行政書士試験は人気資格のため、本屋さんには魅力的なテキストや問題集がたくさん並んでいます。不安から「あれもこれも」と手を出し、結局どれも中途半端になってしまう…これは不合格者の典型的なパターンの一つです。
【私の失敗談】行政書士の時はそうでもなかったのですが、社労士の時はこれでした!基本テキストの他に、評判の良い問題集や一問一答集、予想模試など、次々と新しい教材に手を出してしまいました。結果、知識が断片的になり、体系的に理解することができませんでした。情報があちこちに散らばってしまい、復習も非効率に…。



ちなみに、社労士は取れずじまいです
【改善策】
- メインテキストは1冊に絞る: まずは決めたテキスト(市販でも通信講座のものでもOK)を徹底的にやり込みましょう。内容を隅々まで理解し、記憶に定着させることが最優先です。
- サブ教材は目的を明確にして使う: 問題演習量を増やしたい、苦手分野を補強したいなど、目的意識を持って補助的に使いましょう。
- 情報を一元化する: 別の教材で得た重要な情報や気づきは、メインテキストに書き込むなどして、情報を集約させると復習しやすくなります。(次の項目で詳しく解説します)
2-6. 「捨て科目」は作らない!不得意分野を放置していませんか?
試験範囲が広い行政書士試験では、「会社法は難しすぎるから捨てよう」「この分野は苦手だから後回し…」と考えてしまう人もいるかもしれません。しかし、合否ライン上にいる受験生にとって、その数点が命取りになる可能性があります。
【私の失敗談】私は民法などの考える系の科目が得意で、会社法などの暗記系の科目が苦手。最初の頃は「最低限でいいや」と半ば諦めていました。でも、模試でいつも会社法の失点が響き、「やっぱりダメだ」と思い直しました。



苦手意識を克服すれば落としにくい分野になりました。
【改善策】
- 全問正解を目指さなくてOK: 苦手分野は、まず基本的な問題を確実に解けるレベルを目指しましょう。多くの人が苦手とする分野だからこそ、少しでも得点できればアドバンテージになります。
- 得意を伸ばすより、苦手を平均点に: [source: 7] 一般的に、得意分野で満点を目指すよりも、苦手分野を平均レベルまで引き上げる方が、少ない労力で点数アップにつながることが多いです。
- 「苦手意識」の方を捨てる: [source: 7] 「嫌だなあ」「難しいなあ」というネガティブな感情が、学習効率を下げていることも。「まずはテキストを読んでみよう」と、少しずつ向き合うことから始めてみてください。意外と理解できる部分があるかもしれません。
【効率爆上げ】ノート、わざわざ作ってない?テキストへの書き込みが最強!
勉強熱心な人ほど、キレイなまとめノートを作ることに時間をかけてしまいがちです。しかし、ノート作りそのものが目的になっていませんか?合格のためには、インプットした知識をいかに効率よく定着させ、アウトプットできるようにするかが重要です。
【私の経験から言えること】 ノートを作る時間があるなら、その時間で問題を1問でも多く解いたり、テキストを読み込んだりする方が、はるかに合格に近づきます。



文具が好きで、文字を書くのも大好き。ノートづくりも好きですが、「ノートづくりは勉強ではない、娯楽」という意識で、アウトプットに力を入れています。
【改善策:テキスト書き込み術】
- 情報をテキストに一元化する:
- 講義で聞いたこと、問題集で間違えたポイント、模試で出た重要論点など、すべての情報をメインテキストに書き込みましょう。
- 復習する時、あちこちの教材を見返す必要がなくなり、圧倒的に効率が上がります。
- 書き込みの具体例:
- マーカーの色分け: 「超重要:赤」「間違えやすい:青」「関連論点:緑」など、自分なりのルールを決める。
- 補足情報の書き込み: テキストの説明だけでは分かりにくい箇所に、具体的な例や図、ゴロ合わせなどを余白に書き足す。
- 過去問出題実績: 該当箇所に「H〇年度 問〇」のようにメモしておくと、頻出度が分かり、学習の優先順位をつけやすくなります。
- 付箋の活用: 特に重要なページや、後でじっくり見返したいページに付箋を貼っておくと、検索性がさらに向上します。
「ノートを作らないと覚えた気がしない」という方もいるかもしれませんが、テキストに直接書き込むことで、「自分だけの最強の参考書」を作り上げる感覚で取り組んでみてください。復習の効率が劇的に変わるはずです!
行政書士試験は怖くない!あなたなら絶対合格できる!
ここまで、見直すべき勉強法のポイントをお伝えしてきました。
行政書士試験は、合格率だけを見ると難関に感じるかもしれません。でも、特別な才能が必要な試験ではありません。市販のテキストや通信講座の教材に書かれている基本的な知識を、しっかりと理解し、記憶していれば、必ず合格できる試験です。
私が合格した平成26年は、記述式の採点基準が厳しく、合格率も6%台と低い年でした。民法の難化も話題になりましたが、そんな年でも、基礎を固め、他の科目(行政法や、易化した会社法など)でしっかり得点できた人は合格していきました。
見たこともないような奇問・難問ばかりが出題されるわけではありません。解けなかった問題の多くは、「一度はテキストで見たはずなのに、ちゃんと理解・記憶できていなかった」だけなのです。
「もう無理だ…」と絶望する前に、もう一度、ご自身の勉強法を冷静に見つめ直してみてください。
量をこなすだけでなく、効率を意識する。 限られた時間で最大限の学習効果を得るにはどうすれば良いか?を常に考えましょう。ダラダラと長時間勉強するよりも、短時間でも集中して質の高い学習を積み重ねる方が、結果的に多くの知識を吸収できます。
スキマ時間で効率学習!オンライン講座という選択肢も
ここまで、独学を前提とした勉強法の見直しポイントを中心にお伝えしてきました。
でも、中には
- 「やっぱり一人だと不安…誰かに教えてほしい」
- 「仕事や家事が忙しくて、なかなか勉強時間が確保できない」
- 「もっと効率的に、最短ルートで合格を目指したい!」
と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
そんな方には、オンライン完結型の通信講座を活用するのも非常に有効な手段です。特に、最近CMでもよく見かける「スタディング」は、忙しい受験生にとって心強い味方になってくれるかもしれません。


私も受験生時代、色々な教材を試しましたが、スタディングのようなサービスが当時あったら、もっと効率よく学習できたかも…!と思います。



今では、勉強で必ずスマホでアプリなどのデジタルツール・コンテンツを使っています。勉強の効率化になくてはならないツールです!
スタディングの大きな魅力は、
- ✅ スマホ一つで完結: 通勤時間や休憩時間、家事の合間など、スキマ時間を最大限に活用して講義視聴や問題演習ができます。机に向かう時間がない日でも、学習を継続しやすいのが嬉しいポイント!
- ✅ 視覚的に分かりやすい講義: ただ授業を録画しただけでなく、オンライン学習に最適化された映像は、初心者でも理解しやすいと評判です。
- ✅ 続けやすい工夫: 脳科学に基づいた記憶を定着させる復習機能や、ゲーム感覚で進められる学習フローなど、モチベーションを維持しやすい仕組みが満載です。
- ✅ 圧倒的な低価格: 予備校に通うことを考えると、経済的な負担が少ないのも大きなメリットです。
「今の勉強法に行き詰まりを感じている」「もっと効率的に、でも着実に合格力を身につけたい」という方は、一度スタディングの無料講座を試してみてはいかがでしょうか? 自分に合うかどうか、気軽にチェックできますよ。
👇 無料でお試しOK!スタディング行政書士講座の詳細はこちら 👇
まとめ:諦めなければ、道は必ず開ける!
行政書士試験に「受からない」と悩む気持ち、痛いほどよく分かります。私も何度も壁にぶつかり、諦めかけました。
でも、正しい方向で努力を続ければ、必ず結果はついてきます。
今回ご紹介した7つの見直しポイントを参考に、ご自身の勉強法を少しだけ変えてみてください。
- 学習スケジュールは具体的で、守れていますか?
- 勉強時間は、本当に足りていますか?
- その時間は、質の高い**「勉強」**になっていますか?
- やる気に頼らず、習慣化できていますか?
- テキストは1冊に絞り、情報を集約できていますか?
- 不得意分野から逃げずに、向き合えていますか?
- ノート作りに時間をかけず、テキストに書き込んでいますか?
一つ一つの改善が、必ずあなたの合格を後押ししてくれるはずです。
この記事が、あなたの再挑戦への、そして合格への一歩を踏み出すきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。
あなたの合格を、心から応援しています!