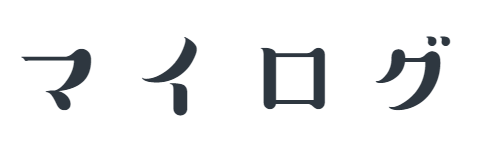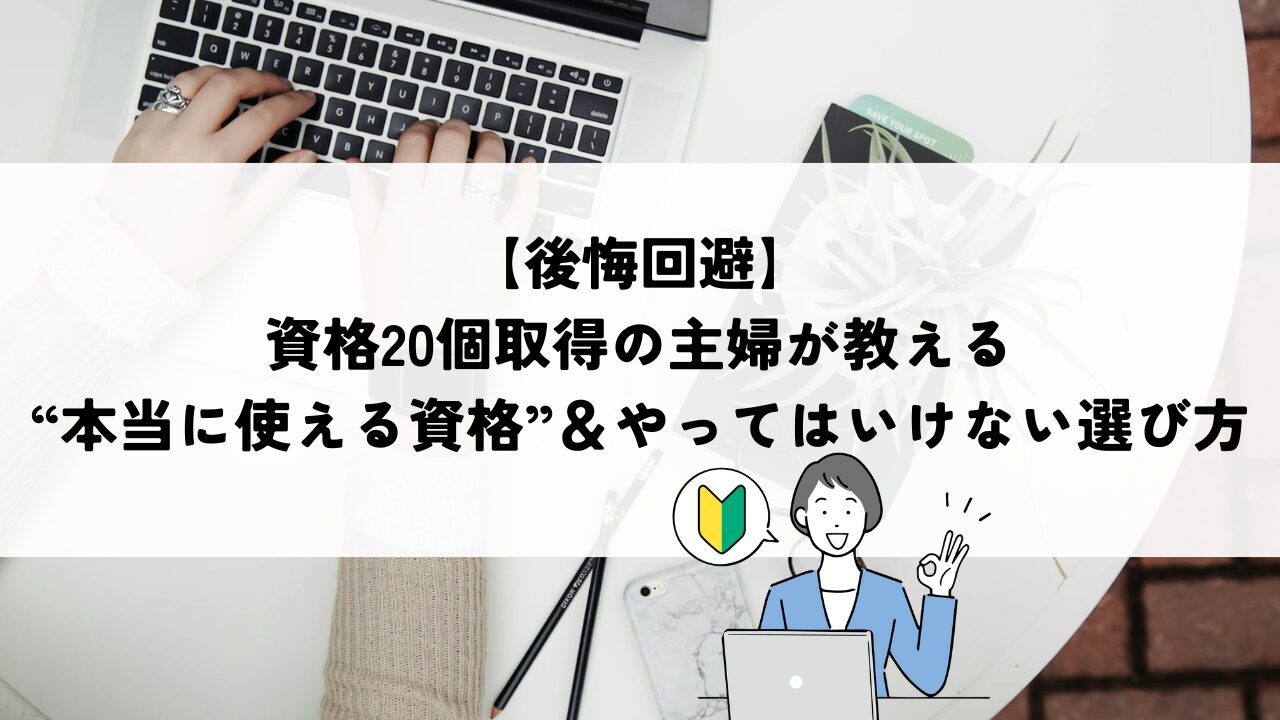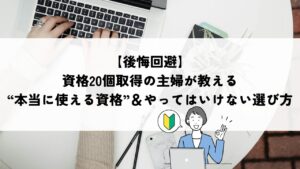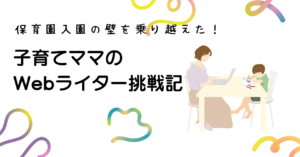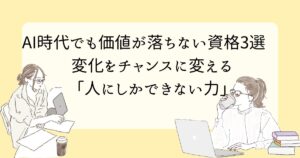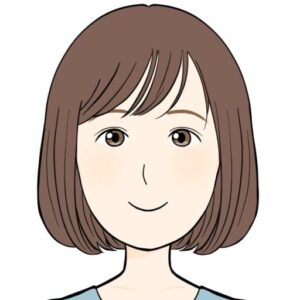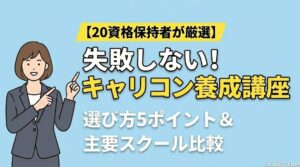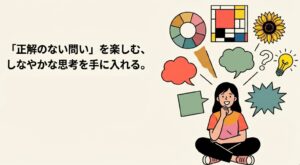まい
まいこんにちは。これまで20個以上の資格を取得してきた資格好き主婦まいです。
「せっかく時間とお金をかけて取った資格が全く役に立たない…」
「資格を取っても就職や転職に有利にならなかった…」



このような悩みを抱えている方も多いのでは。
今日は、「資格って本当に意味あるの?」ってモヤモヤしているあなたへ、私の体験から見えた“資格取得の意義&落とし穴”を赤裸々にお伝えします。



資格好き主婦のまい(@maisawaco)です。
行政書士、宅建、FP2級、簿記3級、カラーコーディネーター、色彩検定2級、福祉住環境コーディネーターなど21の資格を持つ資格好き。
現在はフリーランスライターとWeb制作会社でのパートを兼業中。
資格が「意味ない」と感じる典型的なケース
私は資格について発信して6年目になります。Xでもたくさんのポストを見たり、やりとりをしています。その中で、
「資格を取ったのに、全然仕事に活かせてない…」
「面接でアピールしたけど、反応イマイチだった…」
そんなふうに、資格取得を“ちょっと後悔”している方って、実はけっこう多いのです。



まず、多くの人が資格に失望する典型的なパターンをいくつか紹介します
1. 「何か取らなきゃ」症候群
周囲が次々と資格を取得していくのを見て焦り、明確な目的なく資格取得に走るケース。
例えば、同僚が次々と簿記や宅建を取るのを見て焦り、自分のキャリアプランと無関係の情報処理技術者試験に申し込んだものの、実務でなかなか活かせずに終わることがあります。



就活に際して、とりあえず資格とらなきゃ!と頑張る人も多いね!
2. 安さや手軽さだけで選んだ
「取りやすい資格ランキング」だけを基準に選ぶこと。
例えば、数千円で取れる民間認定の検定試験を取得したものの、実際の就職活動では「この業界で評価される資格は別にある」と気づくこともあります。
3. 仕事や家庭との両立が想像以上に難しかった
勉強時間の確保が難しく、途中で挫折するケース。残業の多い時期に日商簿記2級の勉強を始めたものの、教材を開く時間すら確保できず挫折することもあります。
4. 取得後の活用方法が見つからなかった
資格を取った後、その知識をどう活かすか具体的なプランがなかったケース。
ファイナンシャルプランナー3級を取得したものの、実際の職場では専門知識を生かす機会がなく、資格手当ももらえないこともあります。
5. 労力の割に市場価値が低かった
苦労して取得したのに、思ったほど評価されないケース。半年かけてITパスポート試験に合格したものの、採用担当者からは「基礎的すぎる」と言われ、アピールポイントにならないこともあります。



これらは私自身も経験したことがあります。特に若い頃は「資格=キャリアアップの近道」と単純に考えていましたが、実際はそう単純ではありませんでした。
実は私自身も、「これは失敗だったかも…」と感じた資格がいくつかあります。
以下の記事では、そうしたリアルな体験談を詳しく紹介しています。
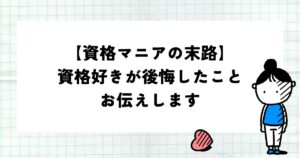
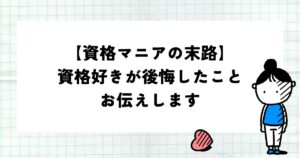
資格取得の落とし穴


資格取得にはいくつかの落とし穴があります。これらを知っておくことで、無駄な時間とお金の投資を避けることができます。
流行り廃りがある
一時期は人気だった資格が、数年後には全く評価されないということもあります。例えば、2000年代初頭にはMCAS(マイクロソフト認定アプリケーションスペシャリスト)が人気でしたが、現在はMOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)に置き換わり、MCASの資格だけを持っていても評価されにくくなっています。
資格だけでは実務能力を証明できない
特に採用担当者や上司が気にするのは「その資格を持っていることで、どんな問題を解決できるか」という点です。例えば、TOEICで高得点を取っても、実際のビジネス英語の場面で使えなければ評価は限定的。



簿記を持っていても20年前の学生の時に取得した資格で、勘定科目がなんだったかすらも思い出せないのならば、実務能力があるとはいえないよね
取得にかかるコストと見返りのバランス
資格によっては、取得に膨大な時間とお金がかかる割に、給与アップや転職に直結しないものもあります。
例えば、中小企業診断士は難易度が高い国家資格ですが、診断士として独立しない限り、資格取得による収入増加は限定的な場合があります。
「使えない資格」の正体とは?
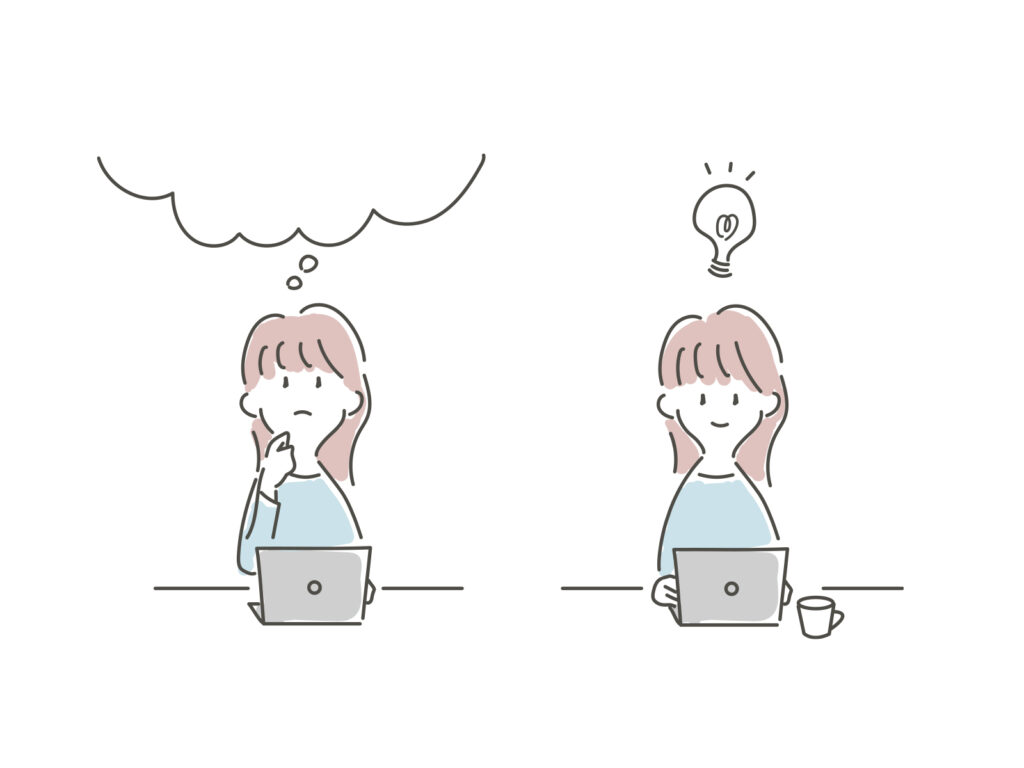
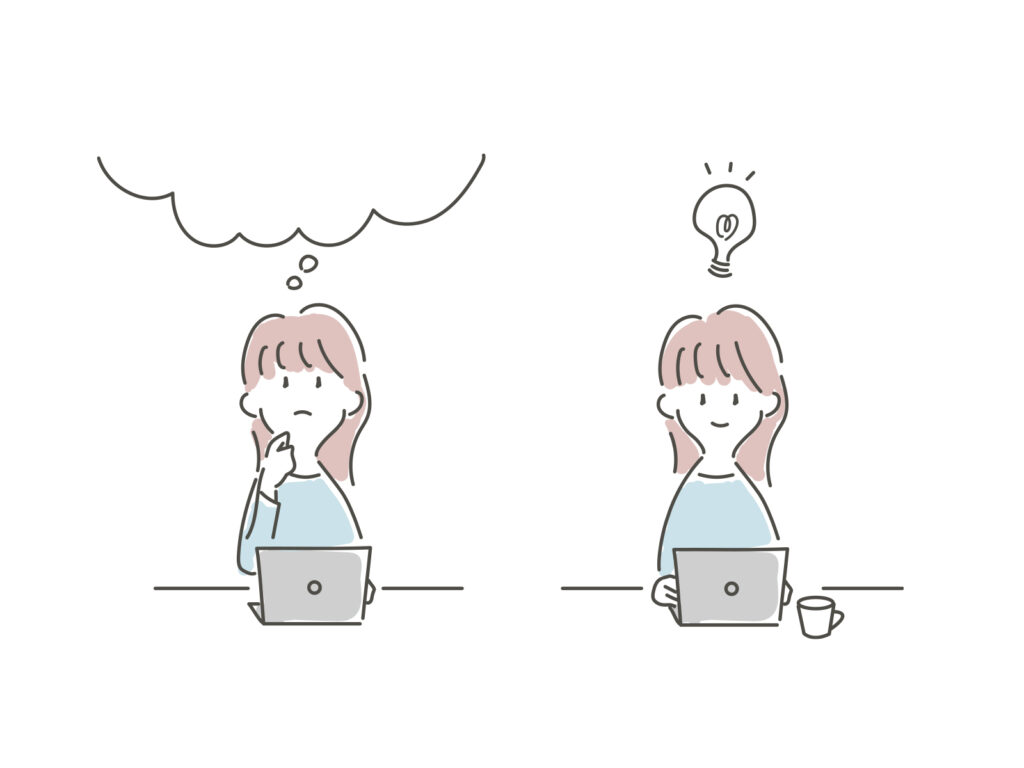
多くの場合、資格自体に価値がないのではなく、その活かし方が定まっていないことが問題です。
医師免許や弁護士資格などの業務独占資格を除いて、ほとんどの資格は「取っただけ」では意味がありません。資格はあくまでツールであり、それをどう活用するかが重要なのです。
例えば、マーケティングを学びたい人がいきなり簿記の資格を取っても、直接的な活用法が見つからず「使えない」と感じるでしょう。これは資格そのものの問題ではなく、自分のキャリアプランとのミスマッチが原因です。
例えば、TOEICで高得点を取得したものの、実際の取引先はすべて国内企業で英語を使う機会がなく、数年経過しても活用できていないということもあります。また、簿記の資格を取得したものの、所属部署では専門の経理担当がおり、知識を生かす場面がほとんどないということもあるでしょう。
「使えない資格」を活きた資格に変える方法
資格が「使えない」と感じる場合でも、以下の方法で価値を見出すことができます。
1. 業務改善の提案に活かす
例えば、ITパスポートの知識を活かして、部署のデータ管理方法の改善を提案する。



ITパスポートは、IT企業では「無駄」「意味ない」と言われる資格ですが、非IT会社、非IT部門の組織では十分に役立つ知識が得られます!



IT化、DX化が進んでいない中小企業などでは、優秀な人材として重宝されることも!
2. 副業や個人プロジェクトに活用する
本業では活かせなくても、副業やフリーランスの仕事で活かすことも可能です。例えば、Webデザインの資格を持っていれば、副業でホームページ制作を請け負うこともできます。



「資格」だけでなく、資格を取得する際に技術の習得ももちろん必要だね。



今は、技術と営業力さえあれば副業で稼げる時代です!
3. 社内勉強会やナレッジ共有の場を作る
取得した資格の知識を活かして、社内勉強会を開催することで価値を生み出すこともできます。
例えば、情報セキュリティの資格を持っていれば、社内のセキュリティ意識向上のためのミニ講座を開催することも可能です。
私が「やめた資格」の話 – インテリアコーディネーターvs宅建士
資格が大好きな私ですが、取得しようかな?と思ってやめた資格も存在します。



一例を紹介します。
以前の職場では資格奨励制度があり、インテリアコーディネーター資格の取得を勧められました。
しかし当時の私は「せっかく難しい資格を目指すなら、より知名度が高く就職にも有利な宅建士の方がいいのでは?」と考え、インテリアコーディネーターの勉強はやめて宅建士を選びました。
これは、インテリアコーディネーターという資格に価値がないと判断したわけではありません。



インテリアが好きなので、興味はもちろんありましt!
単に、当時の自分の価値観や状況(勉強に割ける時間、将来のキャリアイメージなど)に照らし合わせて宅建士を選んだだけです。
選択のポイントとなった要素
- 将来性: 不動産業界は長期的に安定した需要があると判断
- 汎用性: インテリアの知識は宅建業務でも部分的に活かせるが、その逆は難しい
- 認知度: 採用担当者や取引先に説明する際、宅建士の方が認知度が高い
- 資格手当: 多くの企業で宅建士には資格手当がある
結果的には、不動産部署への異動は希望しなかったですが、難関の宅建士資格取得が評価され、当時の昇給率は私が在籍した7年半で1番。手当もつき、しっかりとお金で評価されました。



でも、もし当時の興味や状況が違っていれば、インテリアコーディネーターを選んでいたかもしれません。
思わぬところで役立つこともある
一方で、「使えなかった」と思っていた資格が、思わぬところで役立つこともあります。
私の場合、福祉住環境コーディネーターの資格は長らく活用できずにいました。しかし、現在在籍しているWeb会社でB型支援事業を始めました。



オフィスレイアウトや配置について知識を活かすことができそうです。
ほかにも、例えば、趣味で取った調理師免許が、数年後に社内の健康経営プロジェクトでヘルシーメニュー開発担当になった際に評価されるということもあります。
また、学生時代に取得した色彩検定が、アパレル会社のUI/UXデザイナーとして転職する際の差別化ポイントになることもあるでしょう。
資格の価値は時間とともに変化するということもあるのです。
資格の価値が高まるタイミング
資格の価値が高まりやすいタイミングには以下のようなものがあります。
・法改正や制度変更時: 例えば、税制改正時の税理士資格、法改正時の行政書士資格など
・社会課題が注目されたとき: 例えば、SDGsへの関心の高まりによる環境関連資格の価値向上
・技術革新や新サービス登場時: 例えば、AIブームによるデータサイエンス関連資格の需要増加
・会社のプロジェクト変更時: 例えば、新規事業立ち上げで、過去に取った関連資格が突然脚光を浴びる
資格の「掛け算」で価値を生み出す
特に興味深いのは、一見関連性のない複数の資格を組み合わせる「掛け算」の発想です。
例えば、
- Webデザイン技能検定 × カラーコーディネーター検定 → アクセシビリティに配慮したUI設計の専門家
- 簿記検定 × FP(ファイナンシャルプランナー)→ 中小企業の経営相談に強い税理士事務所スタッフ
- 保育士資格 × 食育インストラクター → 子ども向け食育プログラムの開発者
このような組み合わせは希少性が高く、独自の専門性をアピールできます。



私も執筆協力した本 林雄次先生の「かけ合わせとつながりで稼ぐ 資格のかけ算大全」には、たくさんのかけ算のヒントが掲載されています。おすすめです!
業界別おすすめの資格掛け算
IT業界
- Webディレクター検定 × 色彩検定 → ユーザー体験を重視したWebサイト設計の専門家
- 情報セキュリティマネジメント × 個人情報保護士 → プライバシーに配慮したシステム構築のスペシャリスト
- ITパスポート × ビジネス実務法務検定 → ITコンプライアンスの専門家
営業職
- 宅建士 × マンションリフォームマネージャー → 中古マンションリノベーション専門の不動産営業
- 販売士 × メンタルヘルス・マネジメント検定 → 長期的な顧客関係構築に強い営業担当者
- 貿易実務検定 × TOEIC高得点 → グローバル営業の専門家
事務・総務職
- MOS Excel × 簿記3級 → 数字に強い事務スタッフ
- ビジネス文書検定 × 個人情報保護士 → 情報管理に強い総務担当者
- 秘書検定 × プロジェクトマネージャー → 経営層のサポートに強い高度アシスタント
資格選びで失敗しないための3つのポイント


資格選びで後悔しないためには、以下のポイントを押さえることが重要です:
1. 自己分析を徹底する
自分自身のキャリアの方向性を明確にすることが、資格選びの第一歩です。
自己分析のためのチェックリスト
- 自分が好きな作業や活動は何か?(例:数字を分析する、人と話す、文章を書く)
- 自分の強みと弱みは何か?(例:細部への注意力は高いが、長時間の集中が苦手)
- 5年後どんな仕事をしていたいか?
- 理想の働き方や職場環境は?
例えば、プログラミングに興味があり、論理的思考が得意で、将来はITエンジニアとして自宅でも働ける環境を希望する場合、まずはITパスポートから始めて、基本情報技術者、応用情報技術者へとステップアップするキャリアパスが考えられます。
2. 目的を明確にする
資格取得の目的を明確にすることで、モチベーションも維持しやすくなります。
目的別の資格選びのポイント
- 転職目的: 業界で評価される資格かどうか、求人票での言及頻度
- 昇進・昇格目的: 自社の資格手当や評価制度での位置づけ
- スキルアップ目的: 実務で活かせる知識が得られるか
- 起業・独立目的: 顧客獲得や信頼構築に役立つか
例えば、「営業から経理部門への異動希望」という明確な目的があれば、簿記2級を目指すことは理にかなっています。一方、漠然と「なにか資格があったほうがいい」という理由での行政書士試験挑戦は、挫折リスクが高まります。
3. コスト対効果を考える
資格取得には時間と費用がかかります。それに見合った見返りがあるかを検討しましょう。
コスト対効果の計算ポイント
- 時間的コスト: 学習時間の目安(例:簿記3級なら100時間程度)
- 金銭的コスト: 教材費、講座受講料、受験料の総額
- 期待できるリターン: 資格手当、昇給可能性、キャリアチェンスの広がり
- 維持コスト: 更新料や継続学習の必要性
例えば、中小企業診断士は学習時間1,000時間以上、費用50万円以上かかることもありますが、独立すれば年収アップの可能性がある一方、社内で活かす場合は部署や役職によって評価が大きく変わります。自分の状況に合わせた冷静な判断が必要です。
資格学習を続けるための工夫
資格取得の最大の敵は「挫折」です。以下の工夫で継続的な学習を支援できます。
1. 小さな目標設定と達成の喜び
例えば、「3か月後に試験合格」という大きな目標だけでなく、「今週は第3章まで終わらせる」など、小さな目標を設定します。
2. 学習習慣の構築
「毎日の通勤電車で30分」「土曜の午前中2時間」など、生活の中に学習時間を組み込みます。
3. 仲間作り
同じ資格を目指す仲間との情報交換や励まし合いは大きなモチベーションになります。SNSやオンラインコミュニティを活用しましょう。
4. 自分へのご褒美システム
「1週間続けたらカフェでケーキ」「章末テスト合格でお気に入りの映画鑑賞」など、小さなご褒美を設定します。
資格は「意味ない」のではなく「使い方次第」
資格取得の意義は、単に「持っている」ことではなく、それを「どう活かすか」にあります。明確な目的や活用イメージなく資格を取得すると、確かに「意味がない」と感じるでしょう。
しかし、自分のキャリアや興味に合った資格を選び、それを活かす場を積極的に作っていけば、資格は大きな武器になります。
資格を活かすための実践ステップ
- 自己PR・履歴書での効果的なアピール方法を考える 資格名だけでなく、その資格で身につけたスキルと、それをどう活かせるかを具体的に記述する
- 資格知識を日常業務で積極的に活用する 例:簿記の知識を活かして部署の予算管理を手伝う、英語資格を活かして海外からの問い合わせ対応を買って出る
- 社内外での勉強会やナレッジ共有の場を作る 自分の学んだことを他者に教えることで、知識の定着と価値の創出ができる
- 資格同士の相乗効果を意識したスキルマップを作る 次に取るべき資格が見えてくる
最後に強調したいのは、資格はゴールではなくスタートだということ。資格取得後の行動こそが、その価値を決めるのです。資格取得は単なるチケット取得であり、そのチケットを使って新たな世界に踏み出し、実践で活かしてこそ意味があります。



資格好き私が辿り着いた結論は、「資格そのものに価値はなく、その資格をどう活かすかにこそ価値がある」ということ。
自分自身の目標や状況に合った資格選びをすれば、きっと「取って良かった」と思える資格に出会えるはずです。