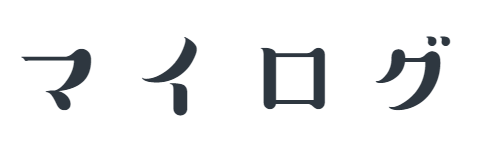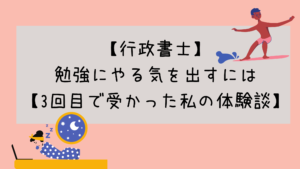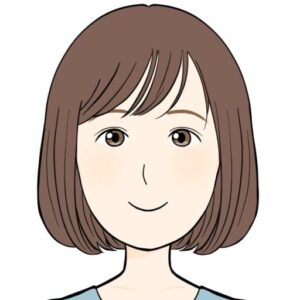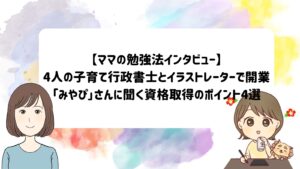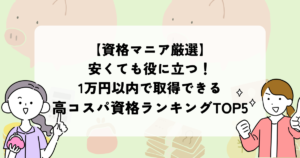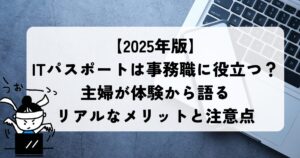ブログ案内犬しろちゃん
ブログ案内犬しろちゃん「色に関わる仕事がしたい!」「色彩感覚を磨きたい!」



そんなあなたにおすすめなのがカラーコーディネーター検定です!
こんにちは。資格好き主婦のまい(@maisawaco)です。私はアドバンスクラスまで合格し、色の勉強が仕事やブログ運営にも役立っています。
この記事では、
- 試験の難易度や受験方式
- 主婦や未経験でも挑戦できる理由
- 取得後に役立てられる仕事・活用事例
をわかりやすくまとめました。
「どんな資格か知りたい」「色彩の知識を身につけたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください!



資格好き主婦のまい(@maisawaco)です。
行政書士、宅建、FP2級、簿記3級、カラーコーディネーター、色彩検定2級、福祉住環境コーディネーターなど15種類の資格を持つ資格好き。
資格ブロガー&ライター歴4年。資格試験のノウハウを発信しています。
| 第58回、第59回2級3級 (スタンダード・アドバンスクラス) IBT・CBT方式試験申し込み期間 | 試験期間 | 受験料(税込) |
|---|---|---|
| 2025年5月16日(金)~5月27日(火) | 6月19日(木)〜7月7日(月) | 【アドバンスクラス】7,700円 【スタンダードクラス】3級5,500円 ※CBT試験はCBT利用料として 別途2,200円(税込)がかかります |
| 2025年9月19日(金)~9月30日(火) | 10月23日(木)~11月10日(月) |
資料請求もちろん無料。デジタルパンフレットは今スグ見れます!おすすめ通信講座は「資格のキャリカレ」
不合格なら「全額返金!」
合格すると「2講座目無料!」



それではいってみよー!
カラーコーディネーター検定とは?今どきの色の資格を解説


カラーコーディネーター検定とはどんなものなかのか、試験概要について解説します。
2020年に大きく変わった!新しい試験制度とは?
カラーコーディネーター検定試験は、2020年よりそれまでの1,2,3級の試験からスタンダードクラス、アドバンスクラスの2クラス制に変更されました。
カラーコーディネーター1級→廃止
カラーコーディネーター2級程度→アドバンスクラス
カラーコーディネーター3級程度→スタンダードクラス
カラーコーディネーター1級はもともと全国でも400〜500名程度しか受験しておらず、難易度も高い試験でした。そちらを廃止し、アドバンスクラス、スタンダードクラスという2つのクラスを設け知識を問う試験となります。
難易度的にはアドバンスクラスが従来の2級程度、スタンダードクラスが3級程度になります。
自宅で受験できるって本当?IBT・CBTの違いと注意点
さらに、2021年度からカラーコーディネーター検定試験を実施する東京商工会議所主催の6つの検定がWeb試験を導入。
IBTという自宅や会社のパソコンから受験できる試験方式と、CBTという全国のテストセンターにあるパソコンで受験ができる試験方式があり、試験期間の希望日に受験ができます。
CBT試験はIBT試験よりも試験センターのシステム利用料(税込2,200円)がかかるという特徴がありますが、自宅等で環境が整っていない場合でも受験しやすいというメリットがあります。自身の状況に合わせて受験方式を選択しましょう。



私は自宅にパソコンがあり、子どもたちもいない時間があるのでIBT方式で受験をしました!


カラーコーディネーター検定試験の概要
カラーコーディネーターの検定試験の概要は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受験資格 | なし |
| 受験地 | 【IBT試験】各自または会社等のパソコン 【CBT試験】全国280のテストセンター |
| 試験日程 | 春期:6月下旬から7月上旬 秋期:10月下旬から11月上旬 |
| 申込期間 | 春期:5月中旬から5月下旬 秋期:9月中旬から9月下旬 |
| 検定料 | 【アドバンスクラス】7,700円(税込) 【スタンダードクラス】5,500円(税込) ※CBT試験は利用料2,200円(税込)が別途かかります |
| 試験時間 | 90分 |
| 試験方式 | 多肢選択方式 |
| 合格基準 | 100点中70点以上 |
| 出題範囲 | 【アドバンスクラス】ビジネスにおける色彩の活用事例など幅広い知識 ・カラーコーディネーターの実務 ・色の見えの多様性とユニバーサルデザイン ・色をつくり、形をつくる 色材、混色から画像へ 等 【スタンダードクラス】日常から見た色彩に関する基礎的な知識 ・生活と色の効用 ・色を自在に操る方法 ・きれいな配色をつくる 等 |
カラーコーディネーター試験は誰でも受験することができます。またアドバンスクラスとスタンダードクラスは併願も可能です。
試験方式は多肢選択方式。マークシートの試験のように、出される選択肢のうち適切なものや不適切なものを選択していきます。
解答は戻ったり見直しをしたりすることができますが、メモは取ることができないので注意しましょう。



IBT試験の様子はこちらの記事をご覧ください
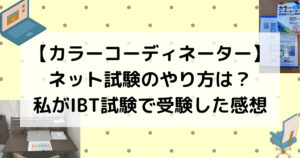
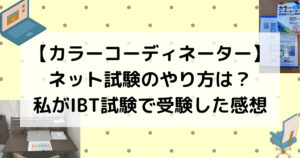
難易度が高い試験ではありませんが、合格基準70点以上なので内容をしっかりと理解しておく必要があります。
アドバンスは難しい?カラーコーディネーターの難易度を分析
カラーコーディネーター検定試験の難易度は(易しい〜やや易しい)程度です。
受験資格もなく、さまざまな業種の人が受験する中で、スタンダードクラス級の合格率は70%、アドバンスクラスの合格率も50%程度となっているのでそれほど難しい試験ではありません。
【スタンダードクラス】
| 試験回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2023年第2シーズン【第55回】 | 2,421人 | 1,785人 | 73.7% |
| 2023年第1シーズン【第54回】 | 2,832人 | 2,118人 | 74.8% |
| 2022年第2シーズン【第53回】 | 2,028人 | 2,295人 | 81.2% |
| 2022年第1シーズン【第52回】 | 3,089人 | 2,448人 | 79.2% |
| 2021年第2シーズン【第51回】 | 2,547人 | 2,112人 | 82.9% |
| 2021年第1シーズン【第50回】 | 2,181人 | 1,832人 | 84.0% |
| 2020年第2シーズン【第49回】 | 4,210人 | 3,044人 | 72.3% |
【アドバンスクラス】
| 試験回 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2023年第2シーズン【第55回】 | 1,230人 | 582人 | 47.3% |
| 2023年第1シーズン【第54回】 | 1,061人 | 537人 | 50.6% |
| 2022年第2シーズン【第53回】 | 1,085人 | 638人 | 58.8% |
| 2022年第1シーズン【第52回】 | 975人 | 613人 | 62.9% |
| 2021年第2シーズン【第51回】 | 764人 | 471人 | 61.6% |
| 2021年第1シーズン【第50回】 | 494人 | 324人 | 65.6% |
| 2020年第2シーズン【第49回】 | 1,115人 | 561人 | 50.3% |
スタンダードクラスは多くの人が受かりますが、アドバンスクラスは1級の内容も含まれているので、勉強している際に難しさを感じる人も多い試験です。
内容も照明光についてなどの物理の分野やデザインの歴史などの暗記分野も多いので、最初はとても「易しい」試験だとは思えません。
しかし、問題自体は意地悪なものが少なく、テキストに書かれていることをそのまま聞かれるので対策はしやすいでしょう。
私は実際に受験してみて、合格率でも学習内容でも、やはり「やや易しめ」の試験だと感じます。



スタンダードクラスもアドバンスクラスも一夜漬けでは受からないことはお忘れなく。頑張らなくて良いので、ぜひ余裕をもって勉強に取り組み対策をしてから臨んでくださいね。
カラーコーディネーターの活かし方は?


次に、カラーコーディネーター検定を活かせる場面、活かし方についてみていきましょう。
インテリア・建築業界
カラーコーディネーター検定は、インテリア・建築業界で活かすことができます。インテリアや家具、カーテン、クロスなどを選ぶ仕事をする際に、全体の雰囲気や色の量をみてコーディネートしたり、顧客に提案をしたりすることができるでしょう。
私も職場でリフォームや建築を取り扱うようになったために取得しました。



事務職でしたが、検定に合格してからリフォーム担当者に内装の色はどれが良いか相談されたことがあります
ファッション・美容業界
カラーコーディネーターの知識はファッションや美容業界で活かすことができます。顧客に似合う色や色の組み合わせの提案を的確に行うことができれば、説得力が上がり、売り上げUPや信頼も獲得できます。
ネイルの配色やメイクにも取り入れることで、技術の専門性が増し、高い評価につながります。
デザイン・商品開発
テキスタイルやホームページ、などのデザインでカラーコーディネーターの知識を活かすこともできます。
色の配色が与えるイメージは購買意欲にもつながるため、商品開発職やマーケティングの分野でも重宝されるでしょう。



私は今Web制作会社で働いていますが、Webデザインや広告制作にも色の知識が必要です!
カラーコーディネーターの勉強法
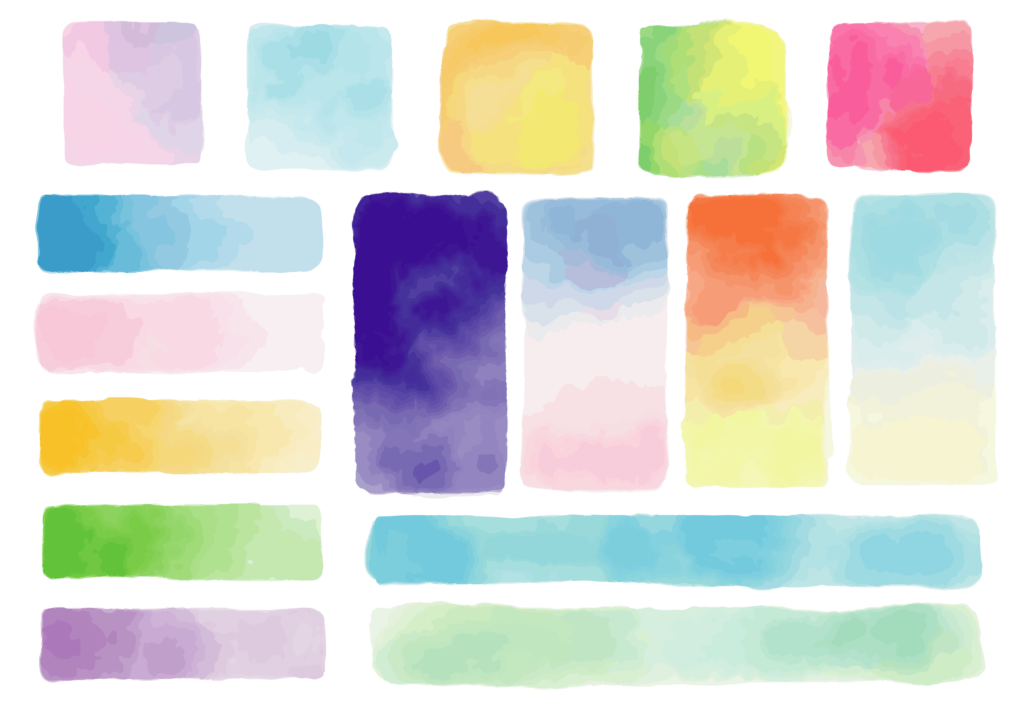
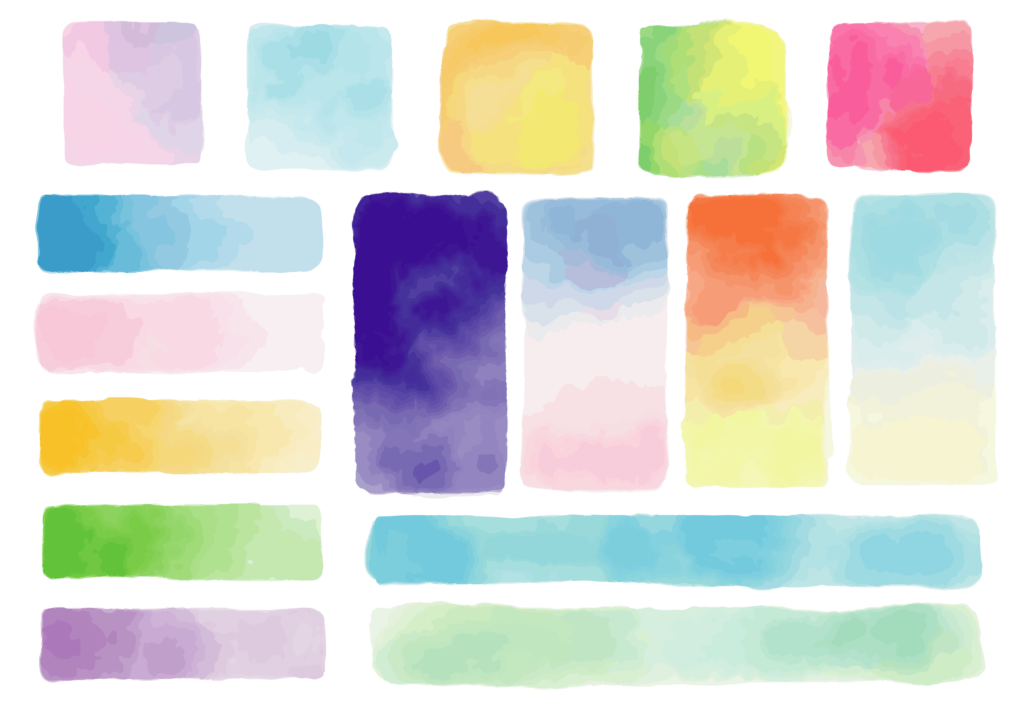
基本的に独学でOK!練習問題の取り寄せも忘れずに
カラーコーディネーター検定試験の対策は、基本的に独学でOKです。
公式テキストの内容をそのまま問う問題が多いので、公式テキストをしっかりと学べば合格できるでしょう。
ただ、アドバンスクラスの場合は公式テキストのボリュームが多く、内容も小難しいのでかなりとっつきにくいのが難点です。実際の問題の難易度よりも難しく感じてしまいます。
そのため、公式テキストに加えて市販のテキストの使用もおすすめです。
公式テキストまたは市販テキスト、またはどちらもに加えて、練習問題の取り寄せは個人的にマストだと思っています。
カラーコーディネーター検定はリニューアル後からまだ試験回数が少ないため、過去問題集が出回っていません。そのため問題演習の機会が少なく、公式テキストのみ使用する方は問題を解かずに試験に挑むことになってしまいます。
ただ、公式で「練習問題」(1回100問の問題が掲載されている冊子)をネットで販売しているので、ぜひそちらを購入するようにしましょう。100問で990円+送料とちょっとお高くはありますが、合格を確実にするために購入しておくべきだと感じました。



私が申し込んだ時はメールからでしたが、今はメールフォームからのお問い合わせになっているようです。ぜひチェックしておきましょう
勉強時間は40時間〜100時間
カラーコーディネーター検定試験の難易度は、「易しい〜やや易しい」レベルです。この難易度の試験は40〜100時間あれば多くの人が合格できます。



スタンダードなら40時間、アドバンスは60時間勉強時間がほしいところです
ただ、勉強に慣れていないと初めのうちは戸惑ったり、なかなか頭に入ってこない可能性もあるので、自分の忙しさや集中力を加味してある程度じゃ余裕を持たせておくことが大切です。
それでも、100時間あれば合格にかなり近づくでしょう!
私がアドバンスクラスを受ける際は、2級を持っていたので35時間ほどの勉強で合格できました。しかし自信満々で受験に挑めたというわけではないので、勉強に自信がある方でも、余裕を持って合格したい方はやはり60時間くらいは時間を確保しておいた方が良いのではないかと思います。
おすすめの教材
おすすめの教材は、「公式テキスト」と市販のナツメ社「スピード合格!カラーコーディネーター」シリーズ、成美堂「1回で合格!カラーコーディネータースタンダードクラステキスト&問題集」のどちらもおすすめです。
おすすめを紹介するのに、1つに絞れないのは良くないと思うのですが、カラーコーディネーター検定のテキストについては「これが断然!絶対おすすめ!」というものがないのが現状です。
というのも、どれも一長一短があるからです。



私は公式テキストよりも安くて問題も掲載されているナツメ社の「スピード合格!カラーコーディネーター【アドバンスクラス】テキスト&問題集」で勉強をしました!
でも、公式テキストじゃないと不安!という方もいらっしゃるだろうなとも感じました
おすすめ教材については、別の記事にしっかりとまとめましたので、教材を選ぶ際にぜひチェックしてみてください!


色彩検定も合わせてじっくり学ぶならキャリカレの通信講座
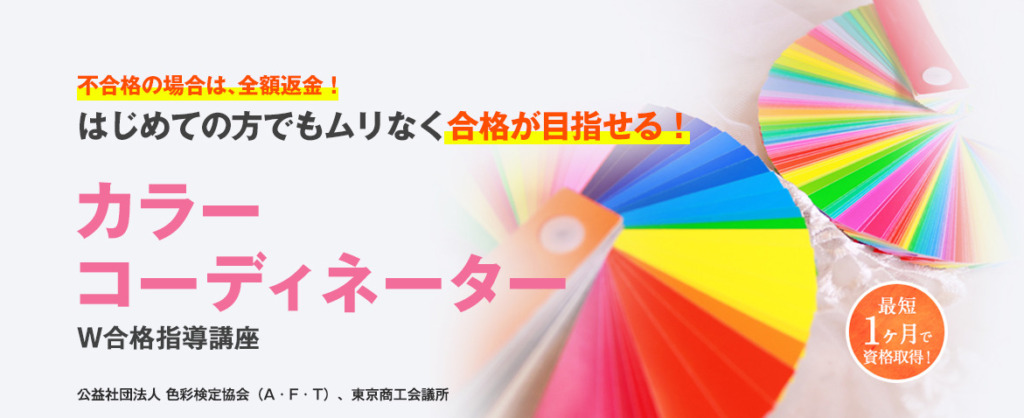
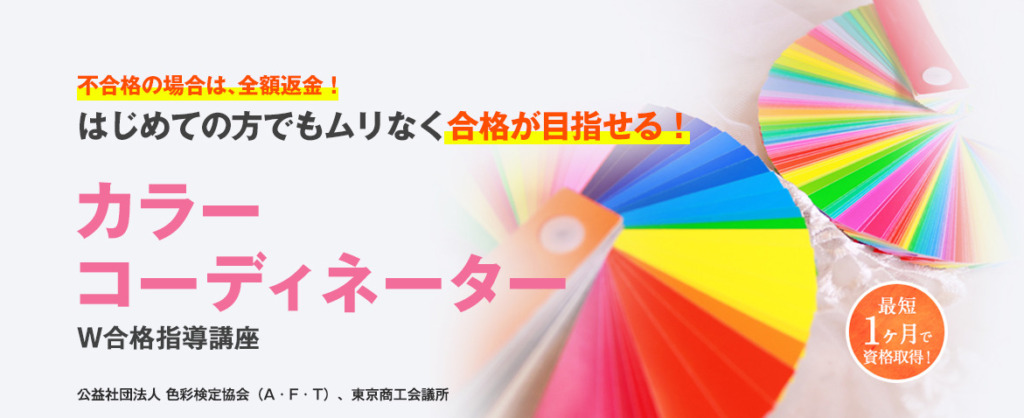
- 独学で挑戦したい方:公式テキスト+過去問でOK
- 時間を効率的に使いたい方:通信講座がおすすめ
です!
資格のキャリカレには、W合格講座があります



私は色彩検定2級も受験しましたが、2つを合わせると本当に色に関する知識が広がり、深まると感じました!おすすめ!
しかもキャリカレは、
- 合格すれば2講座目無料!
- 不合格なら全額返金!
というサポート付きです。
資料請求だけでももちろん可能なので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね!
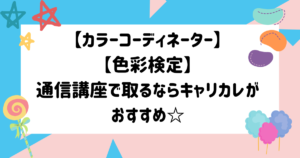
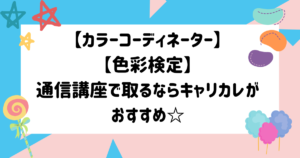
\ 色彩検定との違いも気になる方はこちらの記事もチェック /


カラーコーディネーターについて学んでみよう
カラーコーディネーター検定試験は、色に興味のある方や、キャリアに彩りを加えたい方にぴったりの資格です。
「勉強しやすい」「仕事に活かせる」「主婦でも続けやすい」三拍子そろった資格として、ぜひ一歩踏み出してみてくださいね。
質問などあれば、コメントやX(旧Twitter)でお気軽にどうぞ!



それでは!また別の記事でお会いできたらうれしいです!資格取得がんばりましょー!!!



ぼくもがんばるよー!