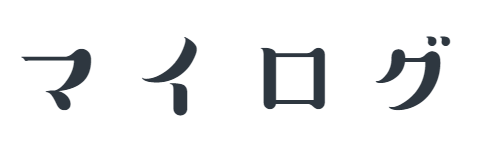まい
まいはじめまして!
マイログ運営者のさわだまい(@maisawaco)です。
当ブログ〈マイログ〉を読んでくださり、ありがとうございます。
ここでは、わたし自身について、そしてこのブログの内容についてご紹介していきたいと思います。
わたしのプロフィール
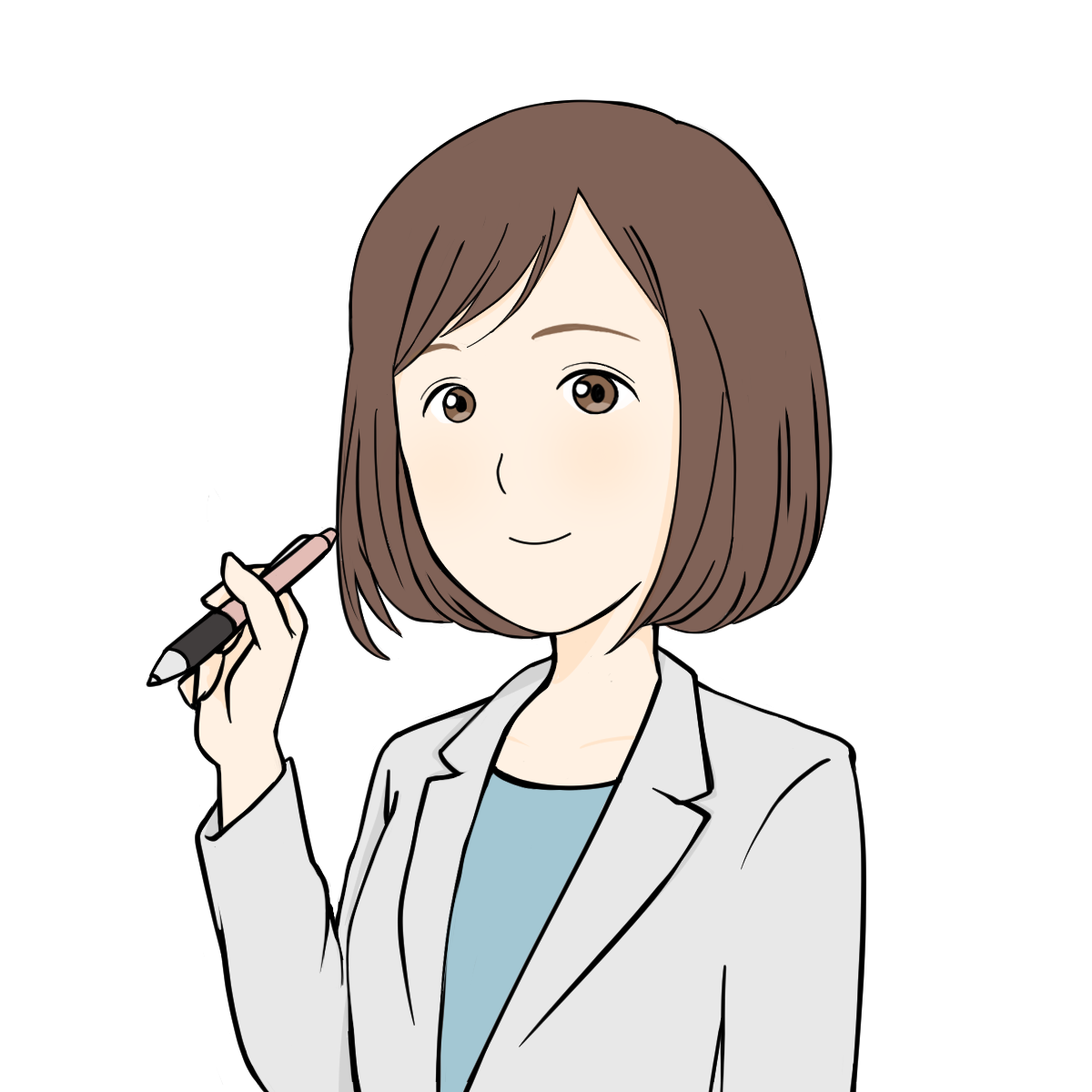
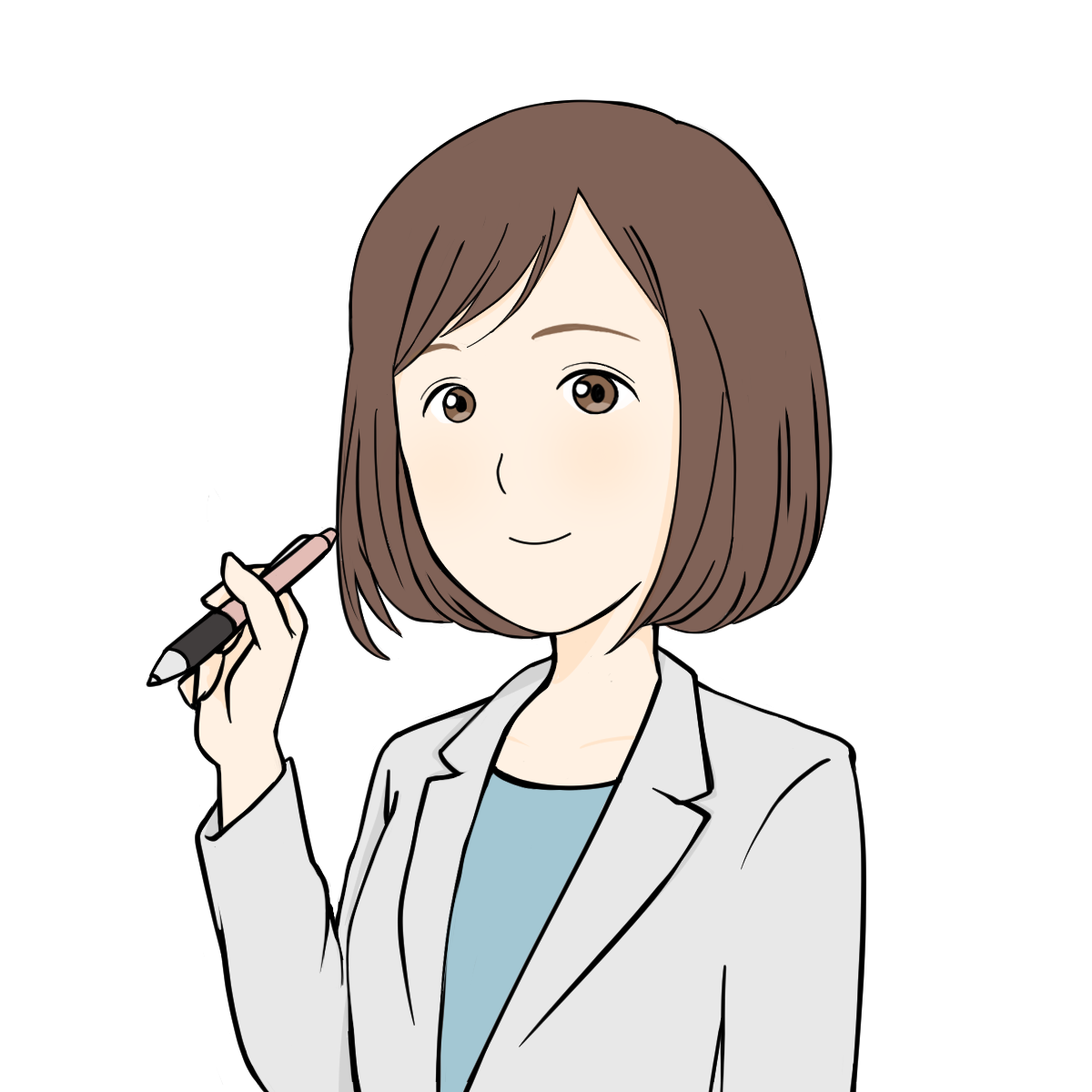
| 名前 | さわだまい |
| 年齢 | 30代後半 |
| 職業 | ライター・Web制作会社でサポート業務 兼業 |
| 家族構成 | 私、夫、長男(6歳)、次男(5歳) |
最近とってもかわいいイラストを描いていただきました。さわだまいと申します。実際は39才、視力だけは良いぼーっとした主婦です。
職歴は、新卒で地方の燃料商社の事務職、後に社労士法人で社労士補助業務。
子どもを産んでからライター、そして、2023年からWeb制作会社(HP制作、Webコンサルなど)でパートでサポート業務を担当させてもらっています。
子どもは6歳と5歳の男の子。夫を含め全員のんびり屋の4人家族です。
そんな私の特徴と言えば、資格が大好きなこと。21種類、24個の資格を持っています。
・行政書士
・宅建士
・ファイナンシャルプランニング技能士2級、3級
・ビジネス実務法務検定2級
・福祉住環境コーディネーター2級、3級
・カラーコーディネーター2級、アドバンスクラス(2022年合格)
・危険物乙種四類
・丙種化学(液化石油ガス)責任者
・第二種販売主任者
・保育士
・ITパスポート
・日商簿記3級
・色彩検定2級
・幼稚園教諭二種免許
・英検準2級
・漢検準2級
・普通運転免許
・Webライター3級
・ビジネス事務検定
・化粧品検定3級
・歯磨きマイスター検定1級
これらの資格を活かし、資格好き主婦としてライター活動、SNSでも情報を発信中。
みなさんと交流できることが、私の生活の楽しみです。



フォローしていただけると、とてもうれしいです!Twitter(@maisawaco)
資格の魅力と女性の働き方について発信したい
さて、このブログについて少しお話させてください。
私がブログ〈マイログ〉を始めたのは、資格の魅力と女性の働き方について発信したいと思ったからです。
***
女性は、ライフステージによって働き方の選択肢が変化します。
結婚などを機に長く務めた職場を退職するケース、産休育休を経て時短勤務またはフルタイムで職場に復帰するケース、パートやアルバイト、フリーランスなど勤務形態を変えざるを得ないケース。
私生活に大きな転機はなくとも、年齢を重ねることで仕事への向き合い方、心身のバランスなどを考えキャリアチェンジする場合もあるでしょう。
私の場合は、結婚によって退職をしなければならない環境にありました。
新卒で勤めた会社は、地元では安定した企業として知られていましたが、女性に関しては当時なんと結婚後も継続して勤めていた方は1名のみ。入社前のリサーチが甘かったのですが、妊娠出産までに肩を叩かれるような職場に勤めていたのです(今はもちろんそんなことはありません)。
仕事自体も一般的な事務職。社会人としての最低限の知識と職場に必要なわずかばかりの専門知識はありますが、たとえば経理職などと比較して、ほかの職場でも活躍できるような汎用性のあるスキルは業務を通しては身につきませんでした。
将来結婚はしたいけれど、何かしらの仕事はしなければならない。今の職場を退職して満足のいく仕事に巡り会えるだろうか……。
何のスキルがく、加えてやりたいこともない自分に、ただただ不安を抱えていました。
そんな時に出会ったのが、「宅建士(当時は宅地建物取引主任者)」の資格です。
***
職場でたまたま取得を推奨されていた「宅建士」。
遠い記憶で『だからあなたも生き抜いて』(大平光代著)で読んだ覚えのある「宅建士」。
調べるうちに、とても有用かつ手に職をつけることができる資格だと知り、漠然とした不安をかき消すために取得しようと決意しました。
しかし、勉強嫌いの私。申し込み後もなかなか勉強に手をつけず、取り組んだのはなんと試験の50日前から(実は7月まで保育士の採用試験を受けていました)。
それでも、50日は必死に勉強をし、独学で一発合格を勝ち取ることができました。


この経験は、私に自信を与えてくれ、将来への希望にもつながります。
***
宅建合格に気を良くしたわたしは、続けて「ビジネス実務法務検定」や「FP3級」「福祉住環境コーディネーター」「カラーコーディネーター」などに挑戦。いずれの試験も合格し、努力が報われる快感を味わっていきます。
これらの資格取得は、何もなかった私の勲章となっていき、気づけばもう不安はなくなっていました。
そうこうしているうちに出会いがあり、結婚が決まると、やはり会社は退社の流れ。
上司からは「優秀だからもったいない」という言葉をいただき(完全に資格のおかげです)、新居の近くの支店で仕事はないかとかけあってくれましたが、定員オーバーとのこと。予定通り7年半勤務した会社を退職します。
***
在職中に、宅建から興味を持った法律分野「行政書士」を取得。その後に「社労士」の勉強を始めていました。
この時、学生以降初めての無職期間があり、やはり一瞬は「就職できるかな」、「決まらなくて、変なところに就職してしまったらどうしよう」という不安が頭をよぎりました。
ただ、ここでも資格が道筋をつくってくれます。
たまたま独身時代から目をつけていた社労士法人でパート求人が出て、時給も高めであり正社員登用もあるためぜひにと就職。
ここでは、優しいチームと堅実な社労士先生に囲まれ、失敗も多数ありながらも勉強になる良い経験をたくさん得ます。
残念ながら、正社員になった後の働き方と自分の今後のライフプランに合わない面があり、妊娠を機にに社労士法人を退職。
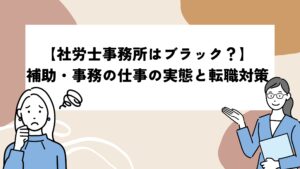
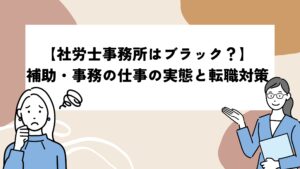
専業主婦を経て、2人目出産以降は在宅Webライターとして働き出します。
***
在宅ワークは、場合によっては賃金が低く、お小遣い程度にしかならないこともありますが、私の場合は「資格がある」という自負もあり、積極的に営業活動をし、扶養ギリギリ程度ですが少ない就労時間で満足のいくお金を得ることができるようになりました。
在宅ワークは性分に合っていて、今でも資格を活かしたライター活動を行っています。
子ども優先で、ゆとりを持った生活は快適でしたが、将来を考えるとWeb関連の知識を得ていきたいと思い、2023年からWeb制作会社で週2~3日働かせてもらっています。
すでに在宅ワークで収入を得ていたことと、資格を持っていていざとなればどこかで働けるという余裕があったため、就職活動ものんびり行うことができ、希望の条件を満たした働きやすい会社に就職することができました。
***
私のこれまでの人生は決して順風満帆ではありませんが、資格の取得と職場選びによって、現在は満足のいくものになりつつあります。
ターニングポイントは、間違いなくあの時「宅建」と出会ったことです。
この資格の魅力、模索して見つけてきた働き方の形を、ぜひ同じように不安を抱える方々にお伝えしたい。
独身の時の将来への不安や、主婦になってからやはり「再就職できるのだろうか」という不安、ママになって家庭との両立が図れるのかといった不安を何とか乗り越えてきた中で、同じような気持ちを抱えている方にエールを送りたい。
そのような気持ちで、マイログを綴っています。
資格については、効率良く取得したと言えるものもあれば、寄り道をしてしまったと悔いが残るものもあります。
失敗談も踏まえながら、ノウハウと体験をみなさんと共有できればと思っています。
どうかみなさんは、私よりも少しでも効率的に、できるだけ近道をして人生を有意義に楽しんでいってください。
マイログがみなさまの糧になり、笑顔につながれば、と願いを込めて。
お付き合いいただければ幸いです。
雑誌掲載
・女性セブン2021年8月26日号「地味だけど確実に稼げる主婦の資格&検定30」
・晋遊舎「LDK」2024年8月号「今、取るべき稼げる資格ランキング」
執筆協力
・『かけ合わせとつながりで稼ぐ 資格のかけ算大全』林雄次著(実務教育出版)
Web記事
・宅建試験の合格に必要な勉強時間・期間は?独学・平均・社会人とケースごとに解説!
・【宅建試験】法令上の制限が頭に入らない!覚え方や攻略法を解説!
イベント
ルクア大阪 妄想ショップ『資格ソムリエ屋さん』2024/1/12
お仕事のご依頼は「お問い合わせ」より承っております。
当サイトで引用している文章・画像について、著作権は引用元にあります。
ただ万が一、不適切な記事や画像、リンク等がありましたら早急に削除等の対応を致しますので